月の朔望周期といえば29.3として表現しているが、現在の精密な計算によればその数値は29.53059日とされている。しかし682年、ユカタン半島のコパンの神官が発見した月の朔望周期は次のように整数の比で表現されているが、そこにはマヤの天体周期に対する精度が伺える。
マヤの神聖暦ツォルキンは260日。人間の染色体の数は46。この46ツォルキン周期は11960日であるが、この日数は月の405朔望周期に相当する。この11960日は、人間が生まれてから32年と273日(月の10公転周期日)たった時の日数である。また土星の公転周期は10759.304日であるが、これを月の朔望周期29.53で割ると、364.35となる。これは土星の1公転が月の1朔望周期のほぼ364倍であるということである。すなわちすでに1年1日法として取り上げたが、月の1朔望周期29.5日が地球の1年365日を介して1日を1年に変換すると、土星の1公転29.5年に対応するのである。
|
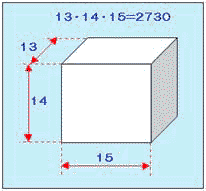 さて前節でフィボナッチ数列の第7項の13と第8項の21の積は273になるということを見た。この月の公転・自転周期27.3日の10進法ホロンである273については、すでにさまざまなことを述べてきた。そこでここではこの27.3の10進法ホロンをさらに別のところからも見出せることを見てみよう。前節のような直方体モデルの3つの辺を左図のように13:14:15としたらその体積はどうなるだろう。13、14、15というと、13と14の2乗の和が地球の1年365日の日数であり(132+142=365)、また15の2乗の方は金星の1年225日になっている(152=225)ということも思い出されるが、この3数を3辺とした立方体の体積は2730となる。すなわち月の100自転・公転周期の日数になっているのである。
さて前節でフィボナッチ数列の第7項の13と第8項の21の積は273になるということを見た。この月の公転・自転周期27.3日の10進法ホロンである273については、すでにさまざまなことを述べてきた。そこでここではこの27.3の10進法ホロンをさらに別のところからも見出せることを見てみよう。前節のような直方体モデルの3つの辺を左図のように13:14:15としたらその体積はどうなるだろう。13、14、15というと、13と14の2乗の和が地球の1年365日の日数であり(132+142=365)、また15の2乗の方は金星の1年225日になっている(152=225)ということも思い出されるが、この3数を3辺とした立方体の体積は2730となる。すなわち月の100自転・公転周期の日数になっているのである。