 (812)数と形とペンターブ・システム (812)数と形とペンターブ・システム
インドのボンベイ地区の一部では、今日でも指によるかなり特殊な数え方をしている。最初に1から5までは、左手の指を次々に立てて数える。5まできたら右手の親指を立てる。それから左手に戻って10まで数え、次に右手の人差し指を立てる。同様にして25まで数えて、右手の指が全部立ってから、さらに自由になった左手を使うと、30まで数えることができる。それをもう1度繰り返せば60までカウントすることができるのだ。この指を使った特殊な数え方は、基本的に5を一括りとした5進法である。しかし52=25の後にさらに5を加算するという数え方で、結果として60進法との互換性もしくは翻訳変換が可能であるという、なかなか興味深い特性を持つものである。
10進法が両手の指を折り数えた数の数え方の結果だとして、それでは片手の指からなる「5進法の痕跡」というものはあるのだろうか。コロンブス以前のメキシコにいたアステカ人の口頭の数え方には、次の表(※)に見るように明確にその5進法的痕跡が見て取れる。またそれ以前からある、ドット1つが1を表しバー1本が5を表すという、マヤ独特の20進法の数表記法にもまた明らかな5進法構造が見て取れる。
| 1:ce |
|
11:matlactli-on-ce |
(10+1) |
| 2:ome |
|
12:matlactli-on-ome |
(10+2) |
| 3:yey |
|
13:matlactli-on-yey
|
(10+3) |
| 4:naui |
|
14:matlactli-on-naui |
(10+4) |
| 5:chicaまたはmaacuilli
|
|
15:caxtulli |
|
| 6:chica-ce |
(5+1) |
16:caxtulli-on-ce
|
(15+1) |
| 7:chica-ome |
(5+2) |
17:caxtulli-on-ome |
(15+2) |
| 8:chica-yey
|
(5+3) |
18:caxtulli-on-yey
|
(15+3) |
| 9:chica-naui |
(5+4) |
19:caxtulli-on-naui |
(15+4) |
| 10:matlactli |
|
20:cem-poualli |
|
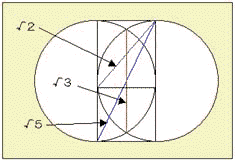 2つの円の中心と円周がそれぞれ重なった形であるベサイカ・ピシスは、「聖なる根」もしくは「神の目」ともいわれているが、このベサイカ・ピシスの上に2、3、5の平方根が見出される。それらは√4すなわち実数の2と共に、1,2,3,4,5の平方根というペンターブシステムを構成している。この3つの平方根の神聖幾何学的な意味、もしくは特性は次の通りである。2の平方根の特性は「発生」である。3の平方根の特性は「3次元空間の形成」である。そして5の平方根その特性は「再生もしくは成長」である。 2つの円の中心と円周がそれぞれ重なった形であるベサイカ・ピシスは、「聖なる根」もしくは「神の目」ともいわれているが、このベサイカ・ピシスの上に2、3、5の平方根が見出される。それらは√4すなわち実数の2と共に、1,2,3,4,5の平方根というペンターブシステムを構成している。この3つの平方根の神聖幾何学的な意味、もしくは特性は次の通りである。2の平方根の特性は「発生」である。3の平方根の特性は「3次元空間の形成」である。そして5の平方根その特性は「再生もしくは成長」である。
(√2=1.41421335…)
(√3=1.7320508…)
(√5=2.2360679…)
またプラトン立体の総数は5つである。その5つの立体のすべての面の数の和は50、すべての点の数の和もまた50であり、5の10進法ホロンとなっている。(すべての面と点の数の和は完璧なる数100である。)またすべての面が正3角形からなる凸多面体の「デルタ多面体」というものがある。これらは全部で8種類存在するのだが、その内の3つは正4面体、正8面体、正20面体である。つまりプラトン立体と重なっていないデルタ多面体はデルタ6、10、12、14、16面体の5つなのである。

(※)表はジョルジュ・イフラー著『数字の歴史』平凡社より
|
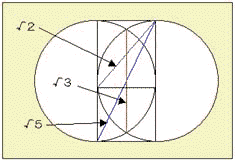 2つの円の中心と円周がそれぞれ重なった形であるベサイカ・ピシスは、「聖なる根」もしくは「神の目」ともいわれているが、このベサイカ・ピシスの上に2、3、5の平方根が見出される。それらは√4すなわち実数の2と共に、1,2,3,4,5の平方根というペンターブシステムを構成している。この3つの平方根の神聖幾何学的な意味、もしくは特性は次の通りである。2の平方根の特性は「発生」である。3の平方根の特性は「3次元空間の形成」である。そして5の平方根その特性は「再生もしくは成長」である。
2つの円の中心と円周がそれぞれ重なった形であるベサイカ・ピシスは、「聖なる根」もしくは「神の目」ともいわれているが、このベサイカ・ピシスの上に2、3、5の平方根が見出される。それらは√4すなわち実数の2と共に、1,2,3,4,5の平方根というペンターブシステムを構成している。この3つの平方根の神聖幾何学的な意味、もしくは特性は次の通りである。2の平方根の特性は「発生」である。3の平方根の特性は「3次元空間の形成」である。そして5の平方根その特性は「再生もしくは成長」である。