 (811)1、2、3、4…そして5=1 (811)1、2、3、4…そして5=1
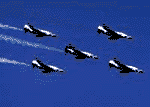 イギリスの城の塔に巣を作ったカラス退治のお話。主人が不意打ちを食らわそうとしても、カラスは賢いので、主人が塔に入っている間は巣を離れていて、そこから出るとすぐに巣に戻ってくる。そこで主人は友人たちに頼んでカラスを騙す作戦に出た。2人で塔に入り、1人が先に立ち去り、もう1人が中に残ってカラスを捕まえようとしたのだ。しかしカラスは騙されなかった。カラスは数を数えられるのだろうか。そこで今度は3人で塔に入り、2人を帰してみた。しかしそれも失敗した。主人は根比べをすることにした。4人で塔に入り、3人を帰すがこれもまた失敗。本当にカラスは人間の数を数えているらしい。主人は長期戦を覚悟し始めた。しかしあらんかな、5人目の計略をもってこの戦いはあっさり終焉を迎えた。カラスは4人と5人の区別ができなかったのである。専門家の意見では、一部の動物の見せる行動の中には、数の観念があるらしいということだ。人間と生活をしている動物や、都会で生きている野生動物などは、人間の「数える」というまさに人為的行動に適応して、直感的把握ではあるだろうが初歩の「数感覚」を体得するらしい。 イギリスの城の塔に巣を作ったカラス退治のお話。主人が不意打ちを食らわそうとしても、カラスは賢いので、主人が塔に入っている間は巣を離れていて、そこから出るとすぐに巣に戻ってくる。そこで主人は友人たちに頼んでカラスを騙す作戦に出た。2人で塔に入り、1人が先に立ち去り、もう1人が中に残ってカラスを捕まえようとしたのだ。しかしカラスは騙されなかった。カラスは数を数えられるのだろうか。そこで今度は3人で塔に入り、2人を帰してみた。しかしそれも失敗した。主人は根比べをすることにした。4人で塔に入り、3人を帰すがこれもまた失敗。本当にカラスは人間の数を数えているらしい。主人は長期戦を覚悟し始めた。しかしあらんかな、5人目の計略をもってこの戦いはあっさり終焉を迎えた。カラスは4人と5人の区別ができなかったのである。専門家の意見では、一部の動物の見せる行動の中には、数の観念があるらしいということだ。人間と生活をしている動物や、都会で生きている野生動物などは、人間の「数える」というまさに人為的行動に適応して、直感的把握ではあるだろうが初歩の「数感覚」を体得するらしい。
 数の認識において4と5の間に何か大きなギャップがあるのは動物だけに限らない。アフリカ、オセアニア、そしてアメリカ大陸の原住民たちの数の概念は、少なくとも今世紀初頭まではかなり初歩的であったという。彼らは1、2、3、4という数しかはっきり認識しておらず、それ以外の数に関してはかなり漠然としたものだったらしい。オーストラリアのアランダ部族は〈1〉を表す数詞と対を表す数詞〈2〉の2つしか知らなかった。〈3〉は1と2、もしくは小さい数と大きい数と言い、〈4〉は2と2、もしくは大きい数と大きい数と表現していた。それ以上はたくさんという言葉になってしまうのだ。民族学者や文化人類学者たちの報告を信用するとすれば、ニューギニアのある原住民や、ブラジルやパラグアイの部族や、アフリカのブッシュマンなども同様のケースであったという。これは現在の我々の太陽における核融合反応(pp反応)によるエネルギーの創出が、原子番号1の水素Hと、2のヘリウムHeによって成されているということを連想させる。また現在の人間が世界を把握するとき、通常すべてに対のものを想定する2元論的発想を用いていることとも関係があるのではないだろうか。つまりそれは我々が未開人などと一方的に呼んでいる人々の問題ではなく、実は我々自身の問題でもあるのだ。 数の認識において4と5の間に何か大きなギャップがあるのは動物だけに限らない。アフリカ、オセアニア、そしてアメリカ大陸の原住民たちの数の概念は、少なくとも今世紀初頭まではかなり初歩的であったという。彼らは1、2、3、4という数しかはっきり認識しておらず、それ以外の数に関してはかなり漠然としたものだったらしい。オーストラリアのアランダ部族は〈1〉を表す数詞と対を表す数詞〈2〉の2つしか知らなかった。〈3〉は1と2、もしくは小さい数と大きい数と言い、〈4〉は2と2、もしくは大きい数と大きい数と表現していた。それ以上はたくさんという言葉になってしまうのだ。民族学者や文化人類学者たちの報告を信用するとすれば、ニューギニアのある原住民や、ブラジルやパラグアイの部族や、アフリカのブッシュマンなども同様のケースであったという。これは現在の我々の太陽における核融合反応(pp反応)によるエネルギーの創出が、原子番号1の水素Hと、2のヘリウムHeによって成されているということを連想させる。また現在の人間が世界を把握するとき、通常すべてに対のものを想定する2元論的発想を用いていることとも関係があるのではないだろうか。つまりそれは我々が未開人などと一方的に呼んでいる人々の問題ではなく、実は我々自身の問題でもあるのだ。
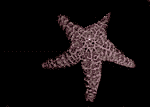 人間がいくつかのものを素早く一瞥した時に、直接的知覚によって判断できるのは普通1から4までの数である(※1)。それより多い数になると、私たちはそれらの集合の要素を意識的に「数える」という作業をしなくてはならない。実際に自分で周囲のものや写真などを見て試してみれば、このことが他人事でなく自分にも当てはまることがすぐに理解ができるだろう。幾何学的認識は右脳の領域でだが、そこには時間がない。一瞥以上の時間をかけて数を数えるのは主に左脳の作業だ。4と5の間には直感的認識と意識的数量識別の界面が存在する。そして右脳と左脳をつないで数を数えることで5と6の界面を超えて進んで行くのだ。そこから時間が流れ出す。もちろん科学的表現では一瞥の瞬間だけでもわずかな時間が必要だということになるが、道具を用いた機械的時間ではなく、等身大の生きた時間が意識の上に流れ出すのである。もちろんこの先の数、6、7、8、9…だけでなく、同時に1/2、1/3、1/4…という逆数、もしくは曲率反転の方向にも、人間の数量把握は左右両方の脳の統合的理解へ向かって進化してきたのだろう。 人間がいくつかのものを素早く一瞥した時に、直接的知覚によって判断できるのは普通1から4までの数である(※1)。それより多い数になると、私たちはそれらの集合の要素を意識的に「数える」という作業をしなくてはならない。実際に自分で周囲のものや写真などを見て試してみれば、このことが他人事でなく自分にも当てはまることがすぐに理解ができるだろう。幾何学的認識は右脳の領域でだが、そこには時間がない。一瞥以上の時間をかけて数を数えるのは主に左脳の作業だ。4と5の間には直感的認識と意識的数量識別の界面が存在する。そして右脳と左脳をつないで数を数えることで5と6の界面を超えて進んで行くのだ。そこから時間が流れ出す。もちろん科学的表現では一瞥の瞬間だけでもわずかな時間が必要だということになるが、道具を用いた機械的時間ではなく、等身大の生きた時間が意識の上に流れ出すのである。もちろんこの先の数、6、7、8、9…だけでなく、同時に1/2、1/3、1/4…という逆数、もしくは曲率反転の方向にも、人間の数量把握は左右両方の脳の統合的理解へ向かって進化してきたのだろう。
例えば電話番号をメモするまでの短時間記憶などでも分かるように、その数を頭の中で繰り返したり声を出したりしながら、覚えていられる限界が普通は8個まである。この1〜4までの瞬間把握もまた、1つ上の認識領域なのではないだろうか。そして皇帝の数といわれる9を加え、両手で10までの数を数えられるように、左右の脳で10進法として数の概念を発達させてきたとも考えられる。
さて「ペンターブ・システム」とは、一言で言えば次元方向をも含めた5進法、もしくは「5即1」というホロニック構造として世界を捉える概念のことである。胎蔵界マンダラや5芒星や直線と凸形線のフラクタルのように、部分を取り出してみるとそこにまた全体のホロン構造が無限に入っているという視覚的・図形的構造そのものをも指す。この考え方を用いれば、漢字文化圏の数の位取り表現が5桁・10000(=104)で1つ繰り上がることや、メートル法で地球の赤道から北極までを10000kmと定めたことなどとの整合性も見て取れる。またその半分の5の4乗が625で、マヤの農耕暦365日と神聖暦260日の和625日と同じ数であることの意味的結びつきなども想起される。過去を顧みれば、60進法の元祖であるシュメールの言語の中にも、一部の数に5を底とした分解の痕跡、すなわち5進法の名残りが認められる(※2)。混在する数の論理と構造…。
しかし重要なことは、これら過去の数のシステムの中にペンターブ・システムやその他の数の構造を再発見することではない。人間がいかなる形でこのようなさまざまな数の抽象的概念を獲得・認識するようになったかの痕跡は、現在のところ発見されてはいない。しかし数に対する認識は人間の精神構造そのものであり、数を数えるという行為は人間の精神活動そのものである。そしてその数に対する人間の捉え方が変化すれば、人間の精神構造そのものも必ず変容するであろう。問題は世界に対する新しい見方の獲得に結びつくように、未来にいかにつなげられるかということである。

(※1)一瞥という表現は眼球運動が開始できないくらいの短時間という意味である。私たちは通常ものを見る場合、目の焦点を非常に素早く動かす事によって数や形や動きを認識している。これができないほどの一瞥では点の数は3〜4個までしか数えられない。たとえ点の残像が網膜の上に残るほど明るくしても、奇妙なことに残像の点を数えても、どの点を数えたか分からなくなってしまうのである。
(※2)ジョルジュ・イフラー著『数字の歴史』平凡社
|