    (711)パラドクスを鏡開く構造 (711)パラドクスを鏡開く構造
かみを求めよ。かみを生きよ。 (すみのお)
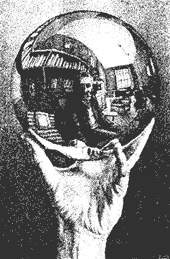 パラドクスという言葉はギリシア語源で「期待に反するもの」という意味だ。経験や常識から「こういうものだ」と思い込んでいたものがひっくり返される。それがパラドクスだ。パラドクスは破壊的にも建設的にも受け止めることができる。それまで積み上げてきたものを無意味・無価値に貶めてしまうこともあれば、それらを否定せずにさらなる創造的活路を見出すこともある。 パラドクスという言葉はギリシア語源で「期待に反するもの」という意味だ。経験や常識から「こういうものだ」と思い込んでいたものがひっくり返される。それがパラドクスだ。パラドクスは破壊的にも建設的にも受け止めることができる。それまで積み上げてきたものを無意味・無価値に貶めてしまうこともあれば、それらを否定せずにさらなる創造的活路を見出すこともある。
オランダの画家M.C.エッシャーの作品の中に「反射球体と手」(1935年)という題のリトグラフがある。自分自身と室内が映り込んでいる反射球体とそれを持つエッシャーの手を描いた作品だ。「平面図形では円がもっとも美しく、空間図形では球がもっとも美しい」といったのはピュタゴラスだが、この球体を見ているとまるで3Dアートで目の焦点深度が合って突如画面が立体的に見える時のように、自分自身がこの球体の内側に入って全く逆側から見ているような感覚を受ける。この球体の表面を通過する時に、意識上で空間曲率の反転が起こるのだ。もしくは内側から飛び出してきて、外側からその透き通った内側を見ているような感覚。これはもちろん等価なのだが。
この絵を見ていると外側から一方的に球体の表面に反射している世界を見ているだけだという思い込みが、曲率が全く逆の中側の世界が透き通った界面を通して見えているようにも思えてくる。エッシャーの目はこの球体に映る自分自身を見ているだけではなく、球体に閉じ込められた逆の曲率側からも世界を見ているのだ。この2つの世界を意識が行ったりきたりしているうちに、これらから等距離の位置から2者を鏡を挟んだ双対の関係と見る視座が立ち上がってくる。この鏡のあわいを開いて、虚像と実像の双方をより豊かな複素空間からどちらにも偏することなく見ているという意識の場…。
これはまた私個人の中では、光速限界のパラドクスに飛び火する。光速限界(ルクシオン領域)を鏡の界面として、物事が光速以下の速さで動くこの私たちの世界(タージオン領域)と、万物が超光速で動くと考えられている理論上の世界(タキオン領域)という構造。このタージオン領域とタキオン領域という二元的関係性を等価かつリバーシブルなものと見る視座は、その界面である鏡(=光速)の中にあり、そこを開き反転して全てを包み込みつつ光で満たすルクシオン領域にしてしまう。
いや実はこの私たちの世界そのものが実はその反転したルクシオン領域なのかもしれない。お正月明けの行事ではないが、鏡開きと表現しうる新しい視座獲得の瞬間。
 同じように2元対立的な世界をつなぐ界面もしくは連結点を反転するという発想で、全てを飲み込むブラックホールと全てを生み出すホワイトホールという少し古い概念を見直してみよう。その2つをつなぐのはワームホール(A)であると考えられている。しかし全く逆にこの私たちにとってノーマルな世界を、ホワイトホールとブラックホールをつなぐワームホール(B)の中の世界であると考えることもできる。その場合は最初に言ったブラックホールとホワイトホールをつなぐワームホール(A)の方がノーマルな世界となる。ワームホール(A)は全然別の次元の狭間にあるのではなく、ただ私たちの世界であるワームホール(B)のまったくの裏側にあって逆方向に流れているだけだとも考えられるのではないだろうか。一体何が誰にとってのノーマルなのだろう。この世界を私たちにとってノーマルな世界と捉えつつ、それをノーマルな世界とのみ見るシステム(宇宙論)の外からもこの世界を見るという視座。 同じように2元対立的な世界をつなぐ界面もしくは連結点を反転するという発想で、全てを飲み込むブラックホールと全てを生み出すホワイトホールという少し古い概念を見直してみよう。その2つをつなぐのはワームホール(A)であると考えられている。しかし全く逆にこの私たちにとってノーマルな世界を、ホワイトホールとブラックホールをつなぐワームホール(B)の中の世界であると考えることもできる。その場合は最初に言ったブラックホールとホワイトホールをつなぐワームホール(A)の方がノーマルな世界となる。ワームホール(A)は全然別の次元の狭間にあるのではなく、ただ私たちの世界であるワームホール(B)のまったくの裏側にあって逆方向に流れているだけだとも考えられるのではないだろうか。一体何が誰にとってのノーマルなのだろう。この世界を私たちにとってノーマルな世界と捉えつつ、それをノーマルな世界とのみ見るシステム(宇宙論)の外からもこの世界を見るという視座。
この幾何学的全体構造はまた人間個人の内世界と外世界にまでスライドする。物質的には自分の肉体と外部の一切という二元性で、界面は皮膚。少し神秘的な人は自分の体外にまではみ出しているオーラや気の辺縁までを自分と見るだろう。心理的には自分の内面世界と、それ以外の他者他物の集合世界。この2者を等価でリバーシブルであると見れれば、鏡越しに相手や世界に自分自身の映り込みを見て、思いやりや共感を感じるだろう。世界を「かみ」と見、自分の自我を「がみ」と見、どちらも否定や無視することなく、その界面で「かみ」と「がみ」を共に見る「かがみ」としてそのあわいを開き、開放系へ反転する鏡開き。
ある時正気を保ちつつ自分が「かみ」であり、今までかみと想定していたものが「がみ」であるという位置の交換の状態に気づくことがある。その時初めて自分も「かみ」であり世界もまた「自分」であるということを、狂気の海で溺れかけつつの神秘体験としてではなく、またただの概念的妄想としてでもなく、意識的に明確に知ることができるだろう。そしてその視座にもまた上位の対があることに気づき、それをも統合すべくさらなる垂上へと向かう道を模索し始めるに違いない。


|