 (671)4分33秒とマイジェネレーション (671)4分33秒とマイジェネレーション
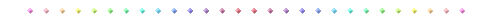
 1952年8月29日、ニューヨーク州ウッドストックのマーヴェリック・コンサート・ホールで、ある曲が演奏された。ピアニストの名はデヴィッド・テュードア。彼はピアノの前に座り、鍵盤のふたを閉じて30秒間動かなかった。それからピアノのふたを開けたかと思うとすぐに閉めて、再びじっと静止し続けた。そして2分23秒後、再度ふたを開け閉めしてから、今度は1分40秒の間微動だにしなかった。この西洋音楽の歴史を変えたともいわれる曲の初演は、テュードアが最後にピアノのふたを開けることで終了した。この3つの楽章からなる曲の初演のオリジナルスコアはそれぞれ33秒、2分40秒、1分20秒となっていたが、その配分はかなりの部分、演奏者の任意でありえた。この現代音楽のタイトルは演奏全体の長さを表わす「4分33秒」といい、作曲者はジョン・ケージといった。 1952年8月29日、ニューヨーク州ウッドストックのマーヴェリック・コンサート・ホールで、ある曲が演奏された。ピアニストの名はデヴィッド・テュードア。彼はピアノの前に座り、鍵盤のふたを閉じて30秒間動かなかった。それからピアノのふたを開けたかと思うとすぐに閉めて、再びじっと静止し続けた。そして2分23秒後、再度ふたを開け閉めしてから、今度は1分40秒の間微動だにしなかった。この西洋音楽の歴史を変えたともいわれる曲の初演は、テュードアが最後にピアノのふたを開けることで終了した。この3つの楽章からなる曲の初演のオリジナルスコアはそれぞれ33秒、2分40秒、1分20秒となっていたが、その配分はかなりの部分、演奏者の任意でありえた。この現代音楽のタイトルは演奏全体の長さを表わす「4分33秒」といい、作曲者はジョン・ケージといった。
200人ほど集まっていた聴衆は、この作品の実験的コンセプトを知るよしもなく、みな不愉快なままいらつき腹を立てていた。同様にジョン・ケージの名前も知らない人に、初めてケージの音楽を聞かせると一様に不快な顔をする。この沈黙の作品「4分33秒」は、音以外の媒体によって分節化された時間を「音楽」と認めること、音というものにかかわらずに「音楽」を再定義することにあった。しかしそれまでの価値観の変革を迫っていると知らされた後でも、それは決して心地よいものではない。それが良いとか悪いとか言うことではなく、私たちはそのようにできているのである。価値観の変革を要求するものを苦もなく次々に受け入れてきたならば、人間という種はとうの昔に絶滅してしまっていたことだろう。
禅の坊さんは自分の弟子たち以外にはめったやたらと禅問答をふっかけはしない。それは現存の意味にも価値を置きつつ、それを超えていく道を選択しているからである。ケージはアーティストとして作品に禅問答を込めてしまったために、すでに現存の価値を手に入れた者にとっては破壊者となり、現存の価値をいまだ体得していない未熟者にとっては、不親切極まりないものとなる。
その昔、ケージの書いたものを読んで女子学生が泣いていた。ケージと懇意だったローラ・クーンが「どうしたの?」と尋ねる。「自分はアーティストになりたくてケージの芸術論を一生懸命勉強してきた。でもこれ以上ついていけない。」「どうして?」「だってケージはギャラリーのような制度は打ち壊せっ!てばかり言ってるでしょ。そういうケージはギャラリーで作品が提示されてるくせに…、なぜ私はいけないの?」…確かにその通りだ。自分の作品がギャラリーで展示されることもまだないのに、最初からそのギャラリーを破壊しろといわれても若い人には分からない。存在自体を否定されているように受け取らざるをえないだろう。破壊すべきものを知るなり持つなりした者に対してでなければ、破壊しろという言葉は意味を成さない。
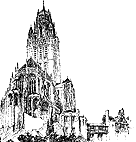 そのローラ・クーンは大学における彼女の講義で、西洋音楽史には12人の歴史を変え、発展させた音楽家がいるという話をした。バッハからはじまってモーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー、ショパン、ブラームス、ドビュッシー、シェーンベルグ、ストラヴィンスキー…とつながって、最後にジョン・ケージが来る。しかし学生たちは変革と発展の歴史としてのおおかたの図式は理解できるが、シェーンベルグからジョン・ケージになるとそこの展開が読み取れない。西洋音楽の最終段階で内側から解体する、伝統そのものをひっくり返してしまって締めくくり、次のフェイズに移行するための「反転」作業。それはしかしこのような形でなく別のありようもあったのではないだろうか。 そのローラ・クーンは大学における彼女の講義で、西洋音楽史には12人の歴史を変え、発展させた音楽家がいるという話をした。バッハからはじまってモーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー、ショパン、ブラームス、ドビュッシー、シェーンベルグ、ストラヴィンスキー…とつながって、最後にジョン・ケージが来る。しかし学生たちは変革と発展の歴史としてのおおかたの図式は理解できるが、シェーンベルグからジョン・ケージになるとそこの展開が読み取れない。西洋音楽の最終段階で内側から解体する、伝統そのものをひっくり返してしまって締めくくり、次のフェイズに移行するための「反転」作業。それはしかしこのような形でなく別のありようもあったのではないだろうか。
「4分33秒」は「全ての音が音楽である」という、音の聞き方に対する1つの姿勢を悟らせるための公案だった。公案は未知のものに対する時に既知のものをもって望む姿勢自体に目をむけさせるための触媒、もしくは方便だ。日常のあらゆるものが音楽であるという思想は美しい。しかしその思想を体得した人はそこに留まらず、さらなる方向へ歩を進める。全てのものが未知なのだ。そしてそれを知れば既知も新たに息を吹き返す。かくして古くなった公案は捨て去られる。菩薩は新しい生き方を提示しても理解されなければ、なんとかそれを理解できるようにとあらゆる形を試行錯誤する。そしてそれが人々に体現されたら、今度はそれを超えていくことを真剣に願い祈るだろう。
今あえて「4分33秒」を聴こうとは思わない。2度聞こうと思う者もまあいないだろう。その作品が表現しようとしたことのエッセンスは、もはやその作品に直接接しなくても理解しうる。その意味ではあの「4分33秒」という作品はエポック・メーキングであり、時代とケージ自身にとって避けては通れない通過点であったにしても、その作品は時代を画した輝きを放ちつつ、とうに古臭くもなっているのだ。萩尾望都の「ポーの一族」(※1)を繰り返し読む人はいても、今やつげ義春の「ねじ式」(※2)を何度も読み返す人はいないのではないだろうか。そして記念碑としてのみ残ることを作品自体が拒絶するというパラドキシカルな構造。教育の本質は与えられたことをすべて取り去った後に、それでもまだそこに残るものだ。「4分33秒」が、ジョン・ケージという名前が忘れ去られること自体にジョン・ケージは異議を唱えはしないだろう。その後に何が残るかこそが問題なのだ。
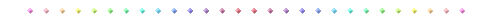
リバプールのキンキーなロックバンドだった「THE
BEATLES」は、有能なプロデューサーのエプスタインによって小奇麗に再デビューし、アメリカの有名なエド・サリバン・ショーというTV番組にもクリーンな優等生然として出演し大好評を博した。一方、モッズ・バンドと目されていた「THE
WHO」はやはり同じTV番組に出演した時、「マ、マ、マイジェネレーション…」と吃るような独特の歌い方をする曲を演奏した。そして彼らは曲が進むにつれ、自分たちの演奏する楽器を壊し始めた。唖然とする司会者や視聴者を尻目に、彼らは徹底的に楽器を破壊し尽くすと退場していった。音楽を演奏する楽器そのものを破壊するというパラドキシカルなパフォーマンスの元祖。彼らも既存の権威や常識そのものに人間として去勢されかけていること自体に腹を立て、システムを抜け出る方向を模索し続けた。セックス・ドラッグ・暴力・オカルト…。
 そして時が流れる。「急ぎ老いる前に死にたい」というメッセージを込めた「マイ・ジェネレーション」という曲でデビューした「ザ・フー」は、やがて自分たちの切り開いた道をやってきた後輩のバンドグループの「ユア・ジェネレーション」という曲に、「生き急ぎ、若く死に、見苦しくない遺体を残す」んじゃなかったのかと揶揄されて、進退を問われることになる。それが原因ではないけれど、「ザ・フー」は紅茶の中に落とされた角砂糖のようにばらけていき、惜しまれつつロック・シーンから退場する。しかしそのリーダーだったピート・タウンゼントは耳が聞こえなくなってもベートーヴェンのように作曲し、ソロ・アルバムを発表し続けている。 そして時が流れる。「急ぎ老いる前に死にたい」というメッセージを込めた「マイ・ジェネレーション」という曲でデビューした「ザ・フー」は、やがて自分たちの切り開いた道をやってきた後輩のバンドグループの「ユア・ジェネレーション」という曲に、「生き急ぎ、若く死に、見苦しくない遺体を残す」んじゃなかったのかと揶揄されて、進退を問われることになる。それが原因ではないけれど、「ザ・フー」は紅茶の中に落とされた角砂糖のようにばらけていき、惜しまれつつロック・シーンから退場する。しかしそのリーダーだったピート・タウンゼントは耳が聞こえなくなってもベートーヴェンのように作曲し、ソロ・アルバムを発表し続けている。
ジョン・レノンが射殺されて久しい。彼の「イマジン」という曲の中のメッセージ。「君たちは僕を夢想者だと言うかもしれないけれど、全ての人が1つである世界、人々がみな信じ合う愛し合う世界を想像してごらん。」今や彼を単なるドリーマーだと考える人は多くはないだろう。それはこの曲も含めて「ビートルズ」の曲がそこここに溢れかえり、繰り返し流れ続けたからでもある。そして次々と革新的作曲をしていったジョンとポールの(そして同時代の多くのアーティストたちの)過去の作品の影響力が、いまや逆に先に進む音楽シーンの手かせ足かせになってすらいるとしたら…。それに執着するのではなく、かといって破壊するのではなく、超えていく道を真摯に模索する者もいるに違いない。
ポップスとクラシック、もしくは西洋音楽の流れそのものとも混同してはいけない問題もある。メタファーとカテゴリーエラーの混在。しかしジョン・ケージがもし西洋音楽史に残らなくても、「それはそれ」だろう。自分を火葬にして骨は森に蒔いてくれと言ったケージは、自分の名前を残すことなぞ考えもしなかっただろう。その昔「オレたちゃ確かにカスさ、しかし太ったブタ野郎どもよりはマシだろう」と言っていたピート・タウンゼント。自分たちの曲を乗り越えようとするよりは、その世界を新しい音楽技術で焼き直し再生産する業界とアーティストたちを見て、いまや自分たちのバックナンバー自体が音楽の進化の障害として用いられていることを悲しんでいるかもしれない、天国のジョン・レノン。ポールは妻に先立たれつつも、曲作りを止めない。脳溢血で倒れる直前まで仕事をしていたジョン・ケージ。彼らを忘れても彼らのいわんとしたことは残る。仏陀を否定しても、仏陀のいわんとしたことは残る。パラドクスを解くとは、超えていくとは、今自分がいる「システム」を否定することなく出ることである。しかも正気を保ったままで。
 ジョン・ケージ。私はこの西洋音楽の歴史を閉じたと言われる現代音楽家が、バックミンスター・フラーや鈴木大拙と永く友人であったことや、「樹の音楽」などと称して植物素材にコンタクトマイクを取り付けて、その電気的に増幅した音が非常に美しい音程となることをとうの昔からやっていたことなどを知る前に、彼の銀河の紋章がKIN260「黄色い宇宙の太陽」、つまりマヤのツォルキン260の一番最後の名を持っていることで興味を持っていた。ちなみにアルバート・アインシュタインも同じ紋章を持っている。それにしても私があの「4分33秒」という作品にひっかかったのは、自分たちが聞いてきた音楽以外の音楽を聴こうとする耳の許容力を全く持たない多くの人に対し、日常的行為の非日常的変換を提示するという彼のコンセプトではなく、なぜそのようなタイトルをつけたかのという疑問からだ。 ジョン・ケージ。私はこの西洋音楽の歴史を閉じたと言われる現代音楽家が、バックミンスター・フラーや鈴木大拙と永く友人であったことや、「樹の音楽」などと称して植物素材にコンタクトマイクを取り付けて、その電気的に増幅した音が非常に美しい音程となることをとうの昔からやっていたことなどを知る前に、彼の銀河の紋章がKIN260「黄色い宇宙の太陽」、つまりマヤのツォルキン260の一番最後の名を持っていることで興味を持っていた。ちなみにアルバート・アインシュタインも同じ紋章を持っている。それにしても私があの「4分33秒」という作品にひっかかったのは、自分たちが聞いてきた音楽以外の音楽を聴こうとする耳の許容力を全く持たない多くの人に対し、日常的行為の非日常的変換を提示するという彼のコンセプトではなく、なぜそのようなタイトルをつけたかのという疑問からだ。
「4分33秒」…それは秒に直せばそれは273秒になる。私はこの数の並びから月の公転・自転周期の10進法ホロンや1年の3/4の273日や、絶対0度である−273.15度Cを連想してしまう。そのタイトルをどうして付けたかは、彼の著作や対話集などで分かるのかもしれない。また誰にもその本意を直接は言わないままなのかもしれない。水の融点/氷点が273.16K(ケルビン度)だから?260+13ではないだろう。それとも全く意味がないのかもしれない。273秒。ここでは新たなる273へ向けて、話を相転移することにしよう。それにしても音楽とは物理的・理論的に扱うよりは、やはり他者の作品を味わい、下手でもいいから自ら演奏・作曲することの方が比ぶべくもなく楽しいことだ。
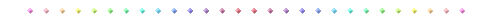
(※1)「月刊少女コミック」に連載された、自らの存在自体を呪いつつ永遠の時を生きる吸血鬼の少年が主人公の伝奇物語。少女漫画に初めて本格派の物語性をもたらしたとの評価を与えられている作品の1つ。
(※2)「ガロ」という雑誌に発表された作品。メジャーな媒体上で、夢や深層心理をそのままマンガとして表現した初めての作品で、当時の読者や作家に少なからずのショックをもたらした。
|
 1952年8月29日、ニューヨーク州ウッドストックのマーヴェリック・コンサート・ホールで、ある曲が演奏された。ピアニストの名はデヴィッド・テュードア。彼はピアノの前に座り、鍵盤のふたを閉じて30秒間動かなかった。それからピアノのふたを開けたかと思うとすぐに閉めて、再びじっと静止し続けた。そして2分23秒後、再度ふたを開け閉めしてから、今度は1分40秒の間微動だにしなかった。この西洋音楽の歴史を変えたともいわれる曲の初演は、テュードアが最後にピアノのふたを開けることで終了した。この3つの楽章からなる曲の初演のオリジナルスコアはそれぞれ33秒、2分40秒、1分20秒となっていたが、その配分はかなりの部分、演奏者の任意でありえた。この現代音楽のタイトルは演奏全体の長さを表わす「4分33秒」といい、作曲者はジョン・ケージといった。
1952年8月29日、ニューヨーク州ウッドストックのマーヴェリック・コンサート・ホールで、ある曲が演奏された。ピアニストの名はデヴィッド・テュードア。彼はピアノの前に座り、鍵盤のふたを閉じて30秒間動かなかった。それからピアノのふたを開けたかと思うとすぐに閉めて、再びじっと静止し続けた。そして2分23秒後、再度ふたを開け閉めしてから、今度は1分40秒の間微動だにしなかった。この西洋音楽の歴史を変えたともいわれる曲の初演は、テュードアが最後にピアノのふたを開けることで終了した。この3つの楽章からなる曲の初演のオリジナルスコアはそれぞれ33秒、2分40秒、1分20秒となっていたが、その配分はかなりの部分、演奏者の任意でありえた。この現代音楽のタイトルは演奏全体の長さを表わす「4分33秒」といい、作曲者はジョン・ケージといった。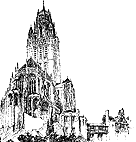 そのローラ・クーンは大学における彼女の講義で、西洋音楽史には12人の歴史を変え、発展させた音楽家がいるという話をした。バッハからはじまってモーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー、ショパン、ブラームス、ドビュッシー、シェーンベルグ、ストラヴィンスキー…とつながって、最後にジョン・ケージが来る。しかし学生たちは変革と発展の歴史としてのおおかたの図式は理解できるが、シェーンベルグからジョン・ケージになるとそこの展開が読み取れない。西洋音楽の最終段階で内側から解体する、伝統そのものをひっくり返してしまって締めくくり、次のフェイズに移行するための「反転」作業。それはしかしこのような形でなく別のありようもあったのではないだろうか。
そのローラ・クーンは大学における彼女の講義で、西洋音楽史には12人の歴史を変え、発展させた音楽家がいるという話をした。バッハからはじまってモーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー、ショパン、ブラームス、ドビュッシー、シェーンベルグ、ストラヴィンスキー…とつながって、最後にジョン・ケージが来る。しかし学生たちは変革と発展の歴史としてのおおかたの図式は理解できるが、シェーンベルグからジョン・ケージになるとそこの展開が読み取れない。西洋音楽の最終段階で内側から解体する、伝統そのものをひっくり返してしまって締めくくり、次のフェイズに移行するための「反転」作業。それはしかしこのような形でなく別のありようもあったのではないだろうか。 そして時が流れる。「急ぎ老いる前に死にたい」というメッセージを込めた「マイ・ジェネレーション」という曲でデビューした「ザ・フー」は、やがて自分たちの切り開いた道をやってきた後輩のバンドグループの「ユア・ジェネレーション」という曲に、「生き急ぎ、若く死に、見苦しくない遺体を残す」んじゃなかったのかと揶揄されて、進退を問われることになる。それが原因ではないけれど、「ザ・フー」は紅茶の中に落とされた角砂糖のようにばらけていき、惜しまれつつロック・シーンから退場する。しかしそのリーダーだったピート・タウンゼントは耳が聞こえなくなってもベートーヴェンのように作曲し、ソロ・アルバムを発表し続けている。
そして時が流れる。「急ぎ老いる前に死にたい」というメッセージを込めた「マイ・ジェネレーション」という曲でデビューした「ザ・フー」は、やがて自分たちの切り開いた道をやってきた後輩のバンドグループの「ユア・ジェネレーション」という曲に、「生き急ぎ、若く死に、見苦しくない遺体を残す」んじゃなかったのかと揶揄されて、進退を問われることになる。それが原因ではないけれど、「ザ・フー」は紅茶の中に落とされた角砂糖のようにばらけていき、惜しまれつつロック・シーンから退場する。しかしそのリーダーだったピート・タウンゼントは耳が聞こえなくなってもベートーヴェンのように作曲し、ソロ・アルバムを発表し続けている。 ジョン・ケージ。私はこの西洋音楽の歴史を閉じたと言われる現代音楽家が、バックミンスター・フラーや鈴木大拙と永く友人であったことや、「樹の音楽」などと称して植物素材にコンタクトマイクを取り付けて、その電気的に増幅した音が非常に美しい音程となることをとうの昔からやっていたことなどを知る前に、彼の銀河の紋章がKIN260「黄色い宇宙の太陽」、つまりマヤのツォルキン260の一番最後の名を持っていることで興味を持っていた。ちなみにアルバート・アインシュタインも同じ紋章を持っている。それにしても私があの「4分33秒」という作品にひっかかったのは、自分たちが聞いてきた音楽以外の音楽を聴こうとする耳の許容力を全く持たない多くの人に対し、日常的行為の非日常的変換を提示するという彼のコンセプトではなく、なぜそのようなタイトルをつけたかのという疑問からだ。
ジョン・ケージ。私はこの西洋音楽の歴史を閉じたと言われる現代音楽家が、バックミンスター・フラーや鈴木大拙と永く友人であったことや、「樹の音楽」などと称して植物素材にコンタクトマイクを取り付けて、その電気的に増幅した音が非常に美しい音程となることをとうの昔からやっていたことなどを知る前に、彼の銀河の紋章がKIN260「黄色い宇宙の太陽」、つまりマヤのツォルキン260の一番最後の名を持っていることで興味を持っていた。ちなみにアルバート・アインシュタインも同じ紋章を持っている。それにしても私があの「4分33秒」という作品にひっかかったのは、自分たちが聞いてきた音楽以外の音楽を聴こうとする耳の許容力を全く持たない多くの人に対し、日常的行為の非日常的変換を提示するという彼のコンセプトではなく、なぜそのようなタイトルをつけたかのという疑問からだ。