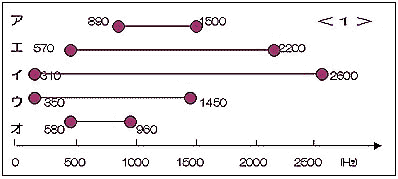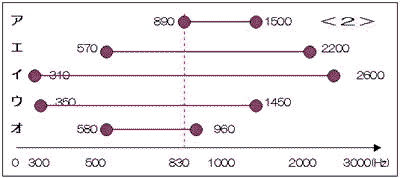(663)5母音の幾何学的対称性 (663)5母音の幾何学的対称性
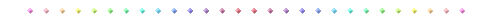
Aは黒、Eは白、Iは赤、Uは緑、O青よ母音らよ
何時の日かわれ語らばや、人知れぬ君らが生い立ちを。
Aはそも、痛ましき悪臭に舞い集う銀蝿の
毛羽立てる黒の胸衣よ、暗き入江よ。
またEは、霞と天幕の純白よ、
毅然たる氷河の切っ先、白衣の王者、オンペルのかすかな振え
Iは緋衣、喀かれし血、怒りに或るは
悔悛に酔う人の、美しき朱唇の笑い。
さてUは周知なり、緑なす海原の、かみさびしわななきなり
獣たちのやすろう牧の平和なり、錬金の術を究むる
博士らの額の皺の平和なり。
Oはそも点のラッパよ、甲高く奇しき響きの、
天界と下界をつなぐ沈黙よ、
−−オメガなり、神の眼の紫の光なり!(※1)
同じ母音がソプラノで歌われる時とバスで歌われる時とでは、強勢している部分音は同じ音高なのだろうか、それとも異なるのだろうか。歌手がある母音を歌う時、どんな音高の時でも一定の音高を強勢しているのだろうか、それとも常に歌っている音高の何番目かの部分音を強勢しているのだろうか。この問題はかつて固定音高論者と相対音高論者の間で議論され続けてきたが、この歌われた母音をフォノデイクという機械を用いて計測・分析してみると次のような結果となった。
| <ソプラノの声音> |
|
<バスの声音> |
| 部分音の番号 |
振動数 |
エネルギー百分率 |
部分音の番号 |
振動数 |
エネルギー百分率 |
| 1 |
308 |
9 |
1 |
154 |
1 |
| 2 |
616 |
6 |
2 |
306 |
3 |
| 3 |
924 |
69 |
3 |
462 |
1 |
| 4 |
1232 |
8 |
4 |
616 |
1 |
| 5 |
1540 |
5 |
5 |
772 |
12 |
| 6 |
1848 |
1 |
6 |
924 |
66 |
| 7 |
2156 |
− |
7 |
1078 |
7 |
| 8 |
2464 |
− |
8 |
1232 |
7 |
| 9 |
2772 |
− |
9 |
1386 |
1 |
この結果から有力な部分音の音高は一定しているということが分かる。そしてこのような分析を広げていった結果、母音に関しては次のようなことが分かった。ma,maw,mow,mooという一連の母音の有力な部分音は、それぞれ910、732、461、326であり、またmat、met、mate、meetという一連の短母音にはそれぞれ2つの有力な音高領域があることが判明した。つまりそれぞれ800と1840、691と1953、488と2461、308と3100である。ところでどのような部分音でも有力になる音高領域をフォルマントというが、全ての母音には一定の音高のブォルマントが2つあるということがほかの分析方法によっても確定された。フレッチャーは母音を分析した数値を以下のような表にまとめた。もっともこの数値は部分音の全てが有力になる音高領域の中央値であり、部分音が有力になる音高領域はかなりの範囲に広がることもありうる。
発音
|
低い振動数 |
高い振動数 |
| u(pool) |
400 |
800 |
| u(put) |
475 |
1000 |
| o(tone) |
500 |
850 |
| a(talk) |
600 |
950 |
| o(ton) |
700 |
1150 |
| a(tather) |
825 |
1200 |
| a(tap) |
750 |
1800 |
| e(ten) |
550 |
1900 |
| er(pert) |
500 |
1500 |
| a(tape) |
550 |
2100 |
| i(tip) |
450 |
2200 |
| e(team) |
375 |
2400 |
oo及びeeという母音は非常に低い音高のフォルマントを持っているので、高い音高でこの母音を発音することはとても難しい。フオルマントの音高よりも高い音はフォルマントの音高範囲内に部分音を持つことがないので、その母音を特徴づける固有の振動数を誘発することができないのである。人間には発声に関して重要な空腔が少なくとも5つある。そのうちの2つは口腔と咽頭であり、下や口唇を動かして容積や口の開け方を変化させて母音を決定させ、残る3つの空腔が音楽的な音色を決定し、声帯が音高を決定させているのである。(※2)
また日本語の波を5母音FFT(Fast Fourier Transform)という機械でフーリエ変換してスペクトルを出し、5母音のそれぞれを特徴づけているフォルマントを取り出してみると次のページ<1>のようになる。ただし男女差及び個人差があるので、その平均値を示すことにする。また音は周波数の各オクターブは対数なので、<2>は対数目盛にして書き直して表してある。
ここで注目したいのは、<2>の真中に太く書いた赤い点線を中心に<ア>⇔<オ>及び<エ>⇔<ウ>が対称的になっている「母音の秩序」である。なお<イ>は正4面体をすぐに連想させるように自分自身と対称である。そしてこの5母音はそのまま5つのプラトン立体の全体と個々の関係ともよく似ている。またこの赤く引いた点線の辺りは若干の個人差はあるものの、だいたい830Hz前後である。この周波数帯域は通常の会話の声・音・言葉の響きでの一つの中心として考えることができるだろう。
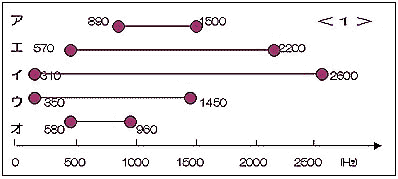
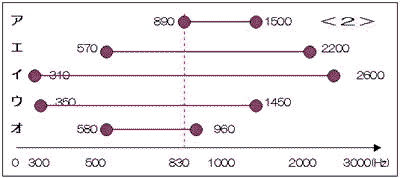
またこの5母音の対称構造性は、日本語の数霊(かずたま)でなぜ50音図のように順番が〈アイウエオ〉ではなく、〈アオウエイ〉として数えるのかの解に、1つの示唆を与えるものであろう。世界の言語の中には母音の数がいろいろあるが、スペイン語の母音の〈a−e−i−u−o〉も、またアルチュール・ランボウの『母音』という詩の「Aは黒、Eは白、Iは赤、Uは緑、O青よ」というフレーズもそれなりにリーズナブルに聞こえる(※1)。
それにしてもなぜ3でも4でも6でも7でもなく5母音なのか。理論的には3母音や9母音の対称的構造ができる。しかし3母音では少なすぎ、9では多すぎて母音同士の区別ができないのである。もっともそのような母音数を持つ言語の人(国)もあるし、対称性が破れて9より少ないが5より多かったり、半母音や二重母音も含むいろいろな言葉ある。例えばアラビア語は3母音である。英語は8〜10母音であり、スウェーデン語では13の母音を持っている。しかし5母音の幾何学的対称性や50音図の構造性などを考えてみると、日本語がいかに整合性のある言語なのかに改めて目をみはらされる。
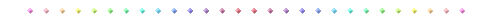
(※1)文頭の引用はランボーの「母音」(Voyelles)という詩(堀口大学訳):フランス語の発音だとAアー、Eウー、Iイー、Uユー、Oオーで、日本のローマ字表記音とずれがある。「見る」人といわれていたフランスの詩人アルチュール・ランボー(18歳で文学に見切りをつけ、アフリカの砂漠商人として生活し、37歳で死亡)の作ったこのソネットに対しては、音響と色彩の間の照応の原理を示そうとしたという説もあれば、単に幼少時に親しんだ色刷りのアルファベット教本の思い出を歌ったに過ぎないと軽く見る向きもある。
(※2)数値データは「音響学」(オーム出版)より。
|