 (620)ピュタゴラス音階と三分損益法 (620)ピュタゴラス音階と三分損益法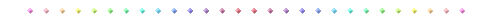
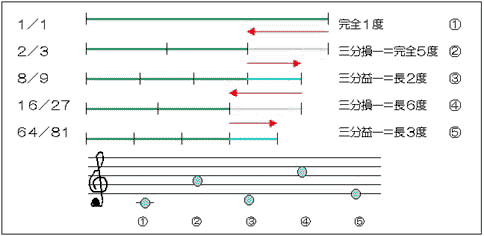
早朝の始発駅。プラットホームに空っぽの電車が滑り込んできてドアが開く。まばらな乗客は三々五々、ゆったりした距離を置いてシートに座っていく。この着席位置の間隔には法則でもあるのだろうか。着席はまず降車時にも便利なドアのすぐ側の席から始まり、次に長いシートの真中か、端から1/3(ということは2/3でもある)が埋まる。もっと混みそうな雰囲気があると1/4(すなわち3/4)の位置にずれる。更に混んでくると同様にしてその間を測るかのようにして座席を埋めていく。もちろん全てがこの限りではない。2人連れ以上は並んで座るだろうし、他人を見る余裕がない者もいる。しかし私にはそれがまるで、乗客がオクターブの中の音階の位置を埋めていく様のように感じられた。確かにあまり近すぎても存在を無視したような気がするし、あまり離れすぎても相手の存在を不快がったかのような気になるけれど、はたしてこれは心理空間においても無意識的に協和音程を作ろうとする幾何学的な平衡感覚なのだろうか。
音程の関係についての記録で現在残っているものは、ピュタゴラス(BC572〜497)の研究が最古のものである。弦が分割された2つの部分から得られる音の間には、弦の張力や太さに関りなくその長さの比が1:1の時は同音、1:2の時は倍音、2:3では5度、3:4では4度の音程関係があるということを示した(※1)。つまり一定の音程は常に簡単な整数比を成すということである。4度と5度は長音階と短音階に共通した音程である。2度も共通しているが、明白な音程ではない。3度、6度、7度は2つの音階において異なるので、<長>及び<短>を付けて区別している。弦長が単純な整数比の場合に快い響きの音程と感じるという事実を、ビュタゴラスは音程関係の原理を説明するのに充分な理由であると考えていた。
 ところで中国には周代よりその記録があり、漢代に成立した「三分損益法」というものがある。これは一定の管(黄鐘〜コウショウ)を「三分損一」「三分益一」の原理を交互に用いて、上の図のように基音から順次、上5度、下4度の音高を生み、それを音高順に並べて十二律を作ったものである。この音律は五声、七声という調性理論を成立させた。原理的にはピュタゴラスの定律法や日本の「順八逆六」の音律算定法(※2)と同じである。日本には奈良時代に入り、「宮調」(キュウチョウ)の五声・七声は「呂」(りょ)、「微調」(チチョウ)の五声・七声は「律」(りつ)と呼ばれていた。しかし元来中国では音律の基準だけでなく、「黄鐘」の律管の長さ・容積・入りうるキビの重さをもって度量衡の基準ともされていた。また「太簇」(タイソウ)を正月として、12音名は12ヶ月各月の名称としても使われていた。 ところで中国には周代よりその記録があり、漢代に成立した「三分損益法」というものがある。これは一定の管(黄鐘〜コウショウ)を「三分損一」「三分益一」の原理を交互に用いて、上の図のように基音から順次、上5度、下4度の音高を生み、それを音高順に並べて十二律を作ったものである。この音律は五声、七声という調性理論を成立させた。原理的にはピュタゴラスの定律法や日本の「順八逆六」の音律算定法(※2)と同じである。日本には奈良時代に入り、「宮調」(キュウチョウ)の五声・七声は「呂」(りょ)、「微調」(チチョウ)の五声・七声は「律」(りつ)と呼ばれていた。しかし元来中国では音律の基準だけでなく、「黄鐘」の律管の長さ・容積・入りうるキビの重さをもって度量衡の基準ともされていた。また「太簇」(タイソウ)を正月として、12音名は12ヶ月各月の名称としても使われていた。
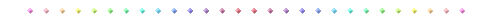
(※1)この同音、倍音、5度、4度の関係は、左図のテトラクティス上の〈1:1〉、〈1:2〉、〈2:3〉、〈3:4〉に同型対応視できる。なおピュタゴラスは5:4の純正長3度音程については(賢明にも?)言及しなかった。ほぼ1000年後の西洋音楽の鍵盤楽器において3度音程を使用するに当たって、システムに過重な負担を与えたために音程を加減する必要を生じさせた。この事に関しては後節で見ていこう。
(※2)「順八逆六」とは12の半音(十二律)による算定法で、基音をCとすれば、上方への順に8つ目の半音がG、(順八)、逆に下方へ6つ目の半音がDとなる。以下同様。
|
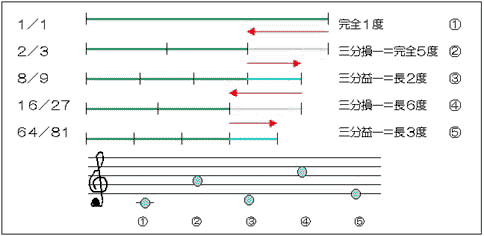
 ところで中国には周代よりその記録があり、漢代に成立した「三分損益法」というものがある。これは一定の管(黄鐘〜コウショウ)を「三分損一」「三分益一」の原理を交互に用いて、上の図のように基音から順次、上5度、下4度の音高を生み、それを音高順に並べて十二律を作ったものである。この音律は五声、七声という調性理論を成立させた。原理的にはピュタゴラスの定律法や日本の「順八逆六」の音律算定法(※2)と同じである。日本には奈良時代に入り、「宮調」(キュウチョウ)の五声・七声は「呂」(りょ)、「微調」(チチョウ)の五声・七声は「律」(りつ)と呼ばれていた。しかし元来中国では音律の基準だけでなく、「黄鐘」の律管の長さ・容積・入りうるキビの重さをもって度量衡の基準ともされていた。また「太簇」(タイソウ)を正月として、12音名は12ヶ月各月の名称としても使われていた。
ところで中国には周代よりその記録があり、漢代に成立した「三分損益法」というものがある。これは一定の管(黄鐘〜コウショウ)を「三分損一」「三分益一」の原理を交互に用いて、上の図のように基音から順次、上5度、下4度の音高を生み、それを音高順に並べて十二律を作ったものである。この音律は五声、七声という調性理論を成立させた。原理的にはピュタゴラスの定律法や日本の「順八逆六」の音律算定法(※2)と同じである。日本には奈良時代に入り、「宮調」(キュウチョウ)の五声・七声は「呂」(りょ)、「微調」(チチョウ)の五声・七声は「律」(りつ)と呼ばれていた。しかし元来中国では音律の基準だけでなく、「黄鐘」の律管の長さ・容積・入りうるキビの重さをもって度量衡の基準ともされていた。また「太簇」(タイソウ)を正月として、12音名は12ヶ月各月の名称としても使われていた。