#150
詩人・ケムイチ君
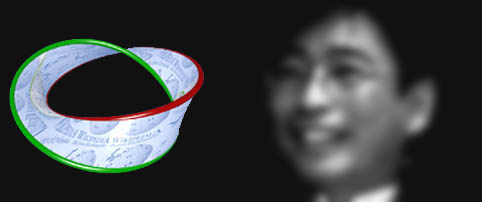
■先日大学時代からの悪親友のケースケベーから超久しぶりに電話があった。これまた悪親友のケムイチクンがガンの末期で入院していて、現在ではもう意識がなくなってしまっているという話だった。思いがけない話である。今春、彼の結婚式に出たばかりだったのに。あの時点で既に痛み止めの薬を使っていたらしい。
■もはや千葉県の某病院に駆けつけても意識の交流はできないし、この時点では既にこの世の人ではないかも知れない。しかし「絶望的」という言葉とは全く違う感慨がある。前世紀末に父親が他界した時の感覚に似ているのかな。悲しいとか遣り残したことがあって悔いが残るとかいう類のネガティブ感覚ではないのだ。
■というか、いつもすぐそばにいる感じ。いつでも会える感じ。私の妄想モードなのかも知れないけれど。彼は詩人だった。波乱万丈の生涯だった。自分もいつ他界しても良い感じがする。ずっとしている。いざとなったらまた別かも知れないけれど、自分も他者のそれも、死ぬということ自体に対する恐怖や不安はない。

■「反転」現象の最たるものの1つ。ただ残された者の喪失感はあるのだろう。友人知人の親で病院に入っているケースがかなりある。症状は軽重様々だけれど、何十年も表現されてきている「人生」とか「生命」などという言葉とそれにこびりついているものが、私だけでなく世界標準で変質変容してきている気がする。
■嘘も奇麗事も死にゆく当人には意味を成さない。残された者たちの心根が世間的にも健やかであればいいとは思う。そう思うこと自体も傲慢かも知れないが。近しく生きていた者が見えなくなるということの不思議。その人を見ようと会いに行けばまだ見える、今生に共に生きる人々に対しても悔いなきよう接したい。
■ケムイチ君はやくざや警察とも犯罪を介さずに仲良くなる特性があった。まだ学生の頃、警察が押収した無修正エロビデオを彼がその手のつてで入手したことがあった。それをケイスケベー、私、kohsen氏で、江戸川区の彼のアパートまで電車に乗って見に行った記憶がある。まあ前世期の話は前世の話ということで。

■まだ出来て間もない貸しビデオ屋そのものも非合法すれすれで営業していた古き良き時代の話である。まだヘアー解禁とかですらない。警察が押収した輸入物だった。みんなでお昼は出前を頼んで、食べながら見続けた。「どうも飯食いながら見るもんじゃねぇなあ」と私が言うと「そうでもねーよ」とケースケベー。
■ケムイチ君は警察に後輩がいて、法に引っ掛かる押収したモロビデオが沢山入手できると自慢気に言っていた。見せてくれたビデオたちは洋モノで、スポーツのようにあっけらかんとするSEXに対して、kohsen氏はAVは「やっぱ和物に限るなぁ~」と心から言っていた。確かに情緒や美的セントも不可欠ではあろう。
■自分の名刺に詩人という肩書きを入れ込むのは、当人の自己申告でOKだ。西洋の偉大な過去からの詩人は取りあえず置いておくとして、現在の日本では詩人として職業的にちゃんと生業っている人間は片方の手にも余る数しかないだろう。実際詩人とは職業なのか?経済活動とは別のところの詩人と言う肩書き。

■詩人と言う人種がいるのかも知れないが、昔は少なからずの若者が真剣に詩人になりたくて、ひとりよがりのちょい暗がり系の文字列を連ねていたようだ。大学のゼミでキーツの詩を専攻し、卒論テーマにまでしたのもあって、日本の詩の少なからずは海外の詩人たちとは別物だと確信犯的に勝手に決めつけてもいた。
■私小説的な視野しかない軟弱なセカイ系には少し辟易していたのである。和歌や俳句に限らず、日本には定型の韻文群には事欠かない。素晴らしい文化であり伝統がある。これも詩と括るなら話は別方向に捩れるが、まあ狭い意味での詩の話をしているので、大叙事詩や形而上学の詩なども別枠ということで押し通そう。
■18~19歳の頃、親元を離れて八王子の浅川という少し大きな川の近くにあった、花井荘というアパートの2階の角部屋に住んでいた。ある日真下の部屋にケムイチ君が引越してきた。彼も英文2クラスの同級生で、しょっちゅう文学や芸術関係の話をし、毎晩のように他の悪友たちとも連れ立って川向うまで飲みに出かけた。

■当時、国道16号線沿いに「三福」という飲み屋があった。その2階には長老というあだ名のこれまた級友の悪友が住んでいたが、そのお店の若女将が三枝ちゃんという可愛い18歳の小娘(ごめんよ)だったこともあり、私たちはしょっちゅう入り浸った時期があった。多数入り乱れての色々なドラマがあったのだが、それはまた別所で。
■大学2年の冬の早朝のことだ。カーテンの隙間から庭を見下ろしたら、少しもやのかかった冷気の中で、ケムイチ君がセメント製のゴミ箱の中で何かを燃やしていた。手元にはかなり大量の原稿用紙の束があり、それを次々に燃やしていた。彼がずっと書き続けていた詩の原稿たちだった。遠くで野鳩が鳴いていたのを覚えている。
■彼は詩人に成りたかった。ずっと成りたくてしょうがなかった。彼はそれまでの自分とその作品群に対する思い込みと思い入れと決別し、過去を断ち新たなる詩人として歩み始めるために、全ての作品を燃していたのだった。今思えば女性がらみの情動や衝動もあったのかもしれない。でもはっきり言おう。彼はずっと詩人だった。

■ちなみに私は詩人にだけはなりたくなかったし、なれるわけもないと決めつけていた。20年ほど過ぎて明るく健やかで、しかも知的巨人である河村悟氏に出会うまでは、詩人とは女にフラれ続ける悲惨な存在だという、自己反転的感覚込みの偏見があった。詩人とは成るものではなく、そう生きざるを得ない存在なのだ。
■自分で「自分は美人です」と平然と口にする女の子の感性が私は好きでない。私にとっての美人かどうかは、ほかならぬ私自身が決めるのだ。多分これと良く似た感覚で、「自分は詩人だから…」と言う者の言葉は、恥ずかしくて聞けない癖がある。私にとって詩人かどうかに関してもこの論理は成立するのである。
■そのひとりよがりの王国の真っただ中で、私自身の内面の(自分も含めた)詩人というものに対する思い込みのせいにして、私はケムイチ君は「詩人だった」と今、口にする。生きている間は冗談以外では決して口にしなかった。彼自身も「ぼくは詩人ではないよ」と言っていた。しかし彼はずっと詩人だった。

■ここでは人間誰もが詩人である…などいう混ぜっ返しはなしということで通したい。もっとも人間の人生はどれも自らが命がけで創り続ける作品であるという表現はありだと思う。詩人というのも作品の中の1つという括りもあるだろうが、私の中の詩人とは絶対公言したくない部分が感謝の振動で弔いを奏でている。
■改めて一言。「詩人、さよなら!」
--------------------------------------------------------

(※追記)
■実は私は、昔からこのような思い出がらみで情動失禁のような文章が大嫌いだった。
遥か昔のアイドルが中年になってから再びTVに出て昔の歌を歌っているのを見た時の感覚に似た不快感とでも言えばいいのだろうか。しかしそれでもそれは私の勝手な思い込み感覚であり、そのような人たちはそれなりに止むにやまれぬものがあったのだということは知っていた。
■願わくばこの文章そのものが愚かで年寄りじみた「勇み足」でありますように。いつまでも、いつまでも「勇み足」でありますように。シュールセンチメンタリズム。このださい表現を口にした時、ケムイチ君は笑い飛ばすことなく聞いてくれた。私はもう少しだけ「人間」を生きています。もう少しだけ「人間」を楽しみます。周りの人たちにプラスフルファの笑顔を強制放出します。
2010.08.04
Wednesday
  
|