#101 開放弦として生きる

■人間は楽器であるというメタファー。我に妨げられることなく神の息吹が自然に流れるならば、人は妙なる調べを奏でる楽器となるという表現。そもそも神とは何か、息吹が流れるとはどういうことか、何よりこのメタファー自体が有効なのか…などと突っ込みどころ満載の表現である。しかし一応それらを捨て置いてこの文脈に沿うとするならば、願わくば私は弦楽器でありたいものだ。
■既定の音階や音高に縛られず、フレットやペグに頼ることもなく、電気が断たれたら息が止まる電動でもないような、そんな弦楽器が理想である。必要な時は自らを楽器でもあり演奏者でもある界面存在としてのスタンスで、麗しき調べを紡ぎ出しもするが、普段はそれが自然である開放弦のままで過ごしたい。もちろんそれはただ何もせずに呆けていれば良いということではない。
■普段から張り詰め過ぎていると突然切れてしまうし、弛み切ったままならば腐った音色しか発せられない。演奏者としても演奏される楽器としてもベストに近い状態でいようとするならば、他の弦との調律を随時怠らず、また他の楽器との協和にも備えて、いつでも演奏できる状態下での開放弦状態が理想だということだ。しかし言うは易く行なうは難しである。

■さてメタファーであると最初に言ったけれど、楽器と奏者という関係を精神と肉体、随意筋と不随意筋、意識と無意識などの不均等で非平衡な二対認識の界面としての呼吸や部分活元状態下の指先にまで、隠喩スライドして見るのも悪くない。これまた突っ込みどころ満載状態だが、問題の焦点はその界面で生起する意識的かつ無意識的な現象をどこから見て論じているかである。
■身体知なり未知なる非自己なるものなりと対話するという時、その対話する二者をトポロジー的に等距離から見て、それらの出来事を全体構造の中で捉えられる視座が存在しなくてはならない。それは二者の片方である「私」の視座からの自己言及ではない。そしてパラドキシカルではあるが、それは開放弦状態でなければ語れもしない。ダンスとダンサーをどう見分けるか。
■もしくは演奏中の演奏者と楽器を明確に区別して捉えられるのか。これまたパラドキシカルなことだが、自分がそのような状態であれば、それはすでにもうどうでもいいことである。「神を求めよ、神を生きよ!」という表現が矛盾なく成されるならば、その言葉や認識の論理構造はもういらない。弦楽器ではなく打楽器や鍵盤楽器や管楽器を選択する人には、また異なる見地があるのだろうか。
■開放弦として生きるということ。
2008.11.13 Thursday

 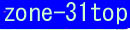 
|