#399
一粒の米すらも残さず自然に頂く美しさ

■今からもう20年ほど前の話だけれど、私は東京の西荻窪というところでYK氏のところで漫画のアシスタントをしていたことがある。当時の私は言うこともろくに聞かずに好き勝手なことばかりやっていたわがまま極まりないアシスタントだった。今思えば本当にいろいろと良くしてもらったもので、心から感謝している。もう1人KT氏というレギュラーのアシスタントと共に町に昼飯を食べに出かけた。
■私たちは3人とも同じ仕出し弁当スタイルのランチを注文した。仕事の合間の気分転換のイベントであるその食事も終わりに近づいた頃、私は自分の手元の弁当箱と2人のそれらを見て少なからずのショックを受けた。その日はからっとした快晴だったので、私の食器はご飯があちらこちらにこびりついていたのだが、彼らはきれいに食べていて米粒1つ残っていないのだ。1人ならまだしも2人共である。
■決して卑しくて1粒たりと残すものかという食べ方ではなく、弁当箱の四角い隅の方からきれいに食べているのだった。せっかちだったり空腹すぎて作法も何もなかった自分の食べ残しがとても無作法に見えた。当時からマイ箸を持って出始めの環境問題に対応していたつもりだったが、食材を作ったり運んだりや調理してくれた人に対する感謝や、食材そのものにたいする思いやりが希薄だった自覚をした。

■まだ小学生に上がる前に、新潟の祖母が「お米の一粒一粒には神様が入っているから一粒だって無駄にしてはならない」と言っていた。私は米どころの農業に従事する者の、信仰にも似た心意気もしくは思い込みだろうと子供心に受け取っていた。20代の半ば過ぎには、自分の世界観の広がりからその汎神論的とも言えるような祖母の言う世界観が素直に受け入れられる心境になっていた。
■当時の私は、食べ物として目の前に出て来たものに対しては、それが生き物としてではなく物のように扱われたものだったり、金になるものとして愛情なく大量生産されたものだったりしても、心から感謝して食べれば自分の血肉となるに違いないと確信していた。同じものを同じように作っても味が違うのだから、同じものでも食べ方によって血肉のなり方が違うと信じていて、何でも美味しく頂いていた。
■それでも目の前で文字通り一粒も残さずにきれいに食べている2人の前で、信条を現実的に行動に移し切っていなかったと反省した自分だった。弁当箱にこびりつきそうな米粒を一粒一粒箸で取りながら食べるという作業が自分にはできなかった。これからもできないだろう。しかしそれでもできるだけそのように心掛けようとひそかに誓った。2人は何事もなかったかのように食べ終えた。

■禅宗の坊さんなら最後にご飯茶碗に白湯を注いで、沢庵の一切れできれいに残った米粒をこそげ取って飲み干すのだろう。またなんとか流の作法の人がお茶漬けを出された時、無造作に端で掻き込んで食べるのを見て、なんてがさつに食べるのだろうと思ったけれど、あとでその箸を見てみたらその先わずか数ミリほどしか濡れていなかったという話を聞いたことがある。真似ではなく私は何ができるだろうか。
■賞味期限を明記してそれを誤魔化したり忠実に守ったりするということ。それ自体のなされている現実の在りよう自体をも問い直して見なくてはなるまい。その記されているラベルに忠実に期限切れの食物を大量に破棄するということもまた、どれだけ全体の中では無駄と矛盾を孕んでいることか。単に否定するのではない。そのような社会の中で何ができるか、どう生きどう変えていくかも考えねばならない。
2007.12.16 Sunday

 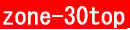 
|