#391
心の闇の中で焚き火の炎を見詰めてみよう(2)

■深夜に猟師が山小屋で焚き火をしていると、いつの間にか何かが囲炉裏の火の向こう側にやって来て、考えていることを次々と読んでいく。それは相手が終いには何も考えられなくなった時に取って食らう化け物だったのだ。そしてまさに猟師に襲い掛かろうとした時、炎の中で突然何かが爆ぜて燃え差しが化け物の顔に当たった。そその化け物は仰天して人間は何も考えなくとも恐ろしいことをすると叫びながら逃げて行った。
■いわゆるさとるのもののけ、もしくはさとるの化け物の話である。思考そのものを次々と読まれて言い当てられると、やがて思考そのものが止まってしまう。その瞬間にこのさとるの物の怪に食べられてしまうのは、身体であるよりもむしろ精神の方だろう。炎を見詰めながら考える時に立ち現れるその化け物は、自分自身の自問自答の影でもあろう。沈黙の中で思考のこだまが止まらなくなり不安や恐怖を生み続ける。
■自分が自分だと認めたくない自分の部分だったり、未だ自分と統合できていないより大きな自分自身であったりとも表現できるが、思考を巡らせることをやめればそれは消えてしまう。もしくは思考の外で起こることに対しては無防備だ。未知の生物とか、人間とは関係ないところでも存在している妖怪として捉えるのではなく、人間意識との界面での現象として捉えるならば、思考しなければ界面から消滅する。

■さとるのもののけの話の本質は、この思いがけぬ自然現象のひと爆ぜによって退散したことで終わるのではなく、むしろそこから始まると考えても良いだろう。堂々巡りに陥りやすい日常的な言語と思考による意識モードが、通常とは異なる領域もしくは形態になるところで感性やより深いところのものが自覚しつつ動き出すのではなかろうか。炎は燃え続けている。思考はない。闇と炎は私と1つ…。
■それにしてもこのようなことを記したとしても、それを読む人が同じ体験をしていなければ言葉で伝えることによる感覚の共用は不可能ではないかと考えてしまった。しかしあの体表で感じる感覚や思考の外側で捉えている印象を共有するのは、時を同じくする必要はないのだと気がついた。後に同様のことを体験して、ああこのようなことを言っていたのかと共有感覚を持てるのは言葉や記録あらばこそだ。
■またすでに同じか似たような全体感覚を知っている人なら、あああの感覚かとすぐに分かり、さらにより深いところへのヒントをくれたりするかも知れない。同じ体験をしても個人的に受け取るものにより価値のあるであろう差異が生じる。注意すべきは言葉のみで理解してしまったつもりになってしまうことだ。頭だけの理解で自足してしまうのは強く戒めねばならないだろう。あの闇と炎をいつも心の中に。
(その3に続く)
2007.12.06 Thursday

 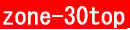 
|