#390
心の闇の中で焚き火の炎を見詰めてみよう(1)

■それにしてもまたあの山中の焚き火を見詰めつつ夜を明かすというイメージが心に浮かぶ。これだけ繰り返し考えるでなく心に浮かぶのだから、私が自覚しているよりも深く私の心の中に残っているものがあるのかも知れない。おそらく長いこと知ってはいたけれど避けてきたことであり、また心の奥深くではその向こうを見るために長いこと求めてもいた何かの突破口もしくは閾域口に軽く触れたということだろう。
■温かい部屋の中や心地良い寝床の中では、真っ暗闇でも不安や恐怖はない。しかし未だ経験のない山奥の森の中で焚き火に向かいながら一夜を明かすのは、なぜイメージしただけでも怖さを感じるのだろう。おそらく自分の家の中や街中でも本当はその恐怖感はなくなってはいないのだろう。ただ雑事や雑音が多すぎて、自らがそれに対峙する姿勢を取れないのだ。いつも心がのどこかが静謐ではない。
■このなかなか絶えて止まない恐怖のイメージは、その少なからずが自らのイメージ力、もしくは妄想も含めた想像力の豊かさゆえと考えたい。意識していなくても無意識領域においてもさまざまな非日常的な草々をイメージしていると、意識と無意識の界面領域で半ば夢見心地にではあるけれど気づくことがある。それは意識に上らなければイメージとすら呼べない様々な心的エネルギーのうねりに過ぎないのだけれど。

■事件や事故などで不本意にも深夜の山中に取り残されたりするのではなく、自らの通常意識の臨界面を敢えて超えようという姿勢ができている状態であれば、その限界を跨いで未知の領域と触れ合うことができる気がする。私はまだ意志が充分強固ではないので、焚き火がなければ意識集中の支点がない。そこで自らの不安や妄想に翻弄されて恐慌に陥ってしまうのではないだろうか。…あの癒される炎の揺らぎ。
■そういえば確実なことがある。闇に対しては言葉が全く非力だということだ。自らの心を奮い立たせたり落ち着かせたりするために声を出したり、頭の中で呪文のように繰り返したりすれば世界は異なった様相を呈するかもしれないけれど、変わったのは自分の方だけで、その結果関係性が変わったように知覚認識されるのだ。できるのは言葉ではない音を聞くことだけだ。山の音、気の音、水の音、心の音。
■焚き火の炎を見詰めている時、自分の背後には自分が光を遮っているがゆえの闇がある。背後を振り返って見ると、そこには今まで自分の背後にあった光の不在がある。いや今でも向き直ったとはいえ自分の存在が作り出している暗闇だ。周りからのわずかな光の反射がそこにはあるだけだ。プラトンの洞窟の喩えでは現世は洞窟の壁面に映る影を見ているが、ここではその影そのものが周囲の闇へと続いている。
(その2に続く)
2007.12.05 Wednesday

 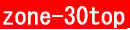 
|