#351 霧雨がただ降っていた

■窓を開けると小雨が降っている。この夏の猛暑が続いた後だけに、その吹き渡り来る風が本当に心地良い。私は子供の頃からずっと晴れ男だった。雨よりも晴れが好きだった。しかし雨が嫌いかといえば決してそうではない。雨が降ると、昔好きになった女の子たちとの記憶が蘇る。決して干からびているわけではない普段の心に、しっとりとした潤いを感じる。もうそれを記しても恥ずかしくない歳になった自分を知る。
■夜遅く、他に誰もいないガラス張りのデパートの屋上から、四方の窓ガラスにへばりつき流れ落ちる雨粒を眺めていた。性的な望みもまだ念頭にない未熟な意識は、その捩れあいつつゆっくり流れ落ちる水滴に囲まれた透明な空間から、町のネオンたちが滲みながら瞬き続けるのを静かに見詰めていた。未来に何があるのかも知らず、過去に誇れる何ものをもまだ成していなかった。ただそこに2人いた。今でもいる。
■また別の時の別の女の子は雨が好きだった。水脈のある地の上に住んでいた。霧や小雨の中を傘も差さずに濡れそぼちつつ歩くのが好きだった。私は雨が好きになった。小学校に入る前に、床に着きながら弟が屋根を叩く雨音を聞くと心が落ち着くんだよねと言っていたことを思い出した。窓の外を静かに流れていく霧雨を眺めつつ、ふと過去なのか未来なのか、別の世界の記憶なのか分からない空間を心が渡った。

■初めて見る猫の親子が足元近くを走り行くのに気づいてここに戻ってきた。浅草の小さな禅寺の駐車場に住み着いたらしい野良猫。仔猫はまだ手のひらサイズだが、足腰はもうしっかりしている。あの脱兎の如き足取り。真っ黒な親猫はじっとこちらを見ている。こいつは危険なヤツなのか、平気なのかを見定める目だ。平気だと伝えたくて近づいた。仔猫が外に飛び出した。小雨がそのちいさな背中にも降る。涼雨一閃。
■幸せに。みんな、幸せに。幸せと言う言葉の意味すら確かには知らないけれど、それでもただ呪文のように、ただ心のなかでリフレインする。幸せに。本当にみんな、幸せに。霧雨に濡れても気付かない程度の、それでも心からの祈りに似たひとりごと。幸せに。本当にみんな、幸せに。傲慢に聞こえるかも知れないけれど、私はいつもいつも幸せです。
(on 90070901)
2007.09.25 Tuesday

 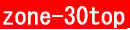 
|