#280 20歳の頃の傲慢なリアリティ

■20歳前には20歳を過ぎてからの自分を想像できなかった。20歳を超えて生きるというイメージが全くなかったので、自分はその前に死ぬのだろうかと漠然と考えてもいた。話をしてみると、同い年の友人達もそのような感覚は共有していた。未来を様々に思い描くこともあったけれど、そのほとんどは妄想やただの概念ばかりでリアリティが無かった。ただその頃の感性や思考力は一番強かったと今でも信じている。
■もちろんそれは今だからそう評価するのであって、当時は自分の感性や思考能力に対して絶対的な自信を持っていた。もちろん何の根拠もないのだけれど、それでもその意識は揺ぎ無かった。自分の美的感覚は誰が何と言おうと絶対であり、自分がダサいと感じるものはダサかった。傲慢であることは自覚できたので、その感覚をひたすら隠してはいた。今だからひとりよがりだったとも評することもできるけれど。
■他者の気持ちに共感する能力がなかったのだが、そのこと自体に思い至らなかった。自分の溢れ出る感性や自己増殖的に湧き上がる思考への対応でいっぱいいっぱいだったのだ。他者への気遣いや思いやりがなければ、恋愛なども思い通りに行くはずもなかった。恋愛に関して言えば、それは美しい者同士がするものであって、それ以外の者にとっては高嶺の花であり、してもみっともないことだと感じていた。

■いがらしみきおという漫画家の作品に、ラブホテルから出てきたカップルに対してモテない男が「おい、おまえら、やったんだろう、やったんだろう、おいっ」と泣きながらからむシーンがある。また別のシーンでは彼が共に不細工なカップルに対して、やはり泣きながら「本当におめでとう、幸せになれよ」と祝福するシーンがあった。笑えたけれど、共感も持てた。これはある意味で自分自身の姿なのだと。
■自己愛の裏返しであると今なら分かるけれど、当時の私は自分をモテない側の者であると自己評価していた。だから自分を幸せな恋愛をする資格のない者だと考えていた。不細工な者が異性に夢中になっているのをみて、とてもみっともないことと感じていた。また逆に美しい者はどんなに性格が悪くてもしかたがないと思っていた。もちろんそのために加害や被害のトラブルのリスクも含まれて入るのだけれど。
■しかしそれでも自分は憧れる資格くらいはあるとも思っていた。そのあたりから芸術は生まれるのであり、幸せな者は創作などはせず、実生活を謳歌するだろうとも。繰り返して言うが、これは今だから…いや今でなくてもその頃からかなり時間が経って、その考え方や感じ方だけが全てではないと分かったから言えることであり、当時はそれが全てではないと想像することはできても、実感が伴わずにいた。

■若かりし頃の傲慢でありつつそのことに無知な自分の話だから、極力隠し立てしないことにする。恋愛とは関係ない側の者と自分を規定していたくせに、いざ自分にガールフレンドができると今度は、何で他の人たちは恋人がいなくても1人で生きていけるのだろうと不思議に思った。1人者を軽蔑する寸前の優越感。まごうかたなき自己中心の思い上がり感覚だ。それでも世界はぎらぎらと輝いてはいた。
■私のことを考えて真摯に忠告してくれる先輩がいた。その正座しつつ語る先輩の姿を眺めつつ、この人は足が短いなあということばかりを考えていた。そしてその後ろ側にある小さな窓に切り取られた新緑の揺らぐ林と光をぼんやりと眺めていた。本当に私はあそこにいたのだろうか。その記憶だけがあっていなかったのか。それとも心神喪失状態で今もあの場に居続けているのが真実なのかもしれない。
2007.04.21 Saturday

 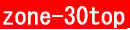 
|