#240 うつろう色あい/息づかいある線

うつろう色あい
■「最近は着物の色がけばけばしくて、汚くなった。」…ある京都の着物職人さんの言葉だ。TVでプリンターのカラーインクやカラーコピーの性能やモニターの高解像度を誇示するために原色が舞い踊るようなCMを良く見かける。一概には言えないが、原色ばかりが入り乱れる画面を見て汚いなあ…というのが私の正直な感覚だった。原色を大胆に使ったゴッホがなぜ日本の浮世絵にあれほど魅せられたのだろう。
■地球の緯度によっても太陽光の映え具合や好みが異なる。アフリカの大平原でマサイ族が原色に近い赤を纏って飛び跳ね踊るのは美しいし、中米や南米の高地にすむ人たちが伝統的な衣装に身を包んで生きているのは好ましい。チベットなどの高地では意識が通常とは異なるので原色に近いインパクトのある色が生存にも不可欠である。土地の色だ。そして日本には日本の伝統的な色の文化というものがある。
■青磁色・群青色・瑠璃色・浅黄色・藍鼠色…。名前からして美しい日本の色たち。人間の可視光線帯域は電磁波の波長がほぼ380〜780ナノメートルだが、その波長のわずか2ナノメートルの違いを私たちは識別できるという。また真っ暗闇の中では慣れればわずか1つのフォトンでも見て取れるそうだ。決して原色が悪いといっているのではないが、近代建築のがさつさと野に咲く小花の繊細さほどの違いがある。

■個々人の既存の感覚帯域を広げる時は、周波数的表現をすればより大きな波長とより細かい波長の方向に自らのバンドを拡張していく方が効果的だ。大もしくは小の一方向だけだと、現実と乖離した理想家や観念論者になるか、日常生活に支障を来たすほどの専門バカか過繊細人間になる。どちらにもその感性を能動的に広げると、それらがまた倍音や協和音的に呼応しあって、受容性も創造性もぐんと広がる。
■原色のように彩度の高い色と渋い色、先進的な色と伝統的な色、同じ色でも適切な明度差・彩度差などがあり、それらの組み合わせとなると、もう超立体的な関係から無数の「いろあい」が生じる。一つ一つの色に呼応する私たちの心。そしてそれらの組み合わせと同じ構造が意識の中にもあるから、私たちの色彩の感性は進化して止まない。さらに聴覚や嗅覚や触覚や味覚も呼応調和させれば限りなく楽しい。
息づかいある線
■斉藤孝は日本画を息の文化、呼吸の文化だという。筆やペンの線はその命の在りようで生き生きもするし、まさに死んだままでもありうる。油絵の筆との根本的な違いの1つは、そのタッチが1度きりか何度も重ねられるかの違いだ。どちらが良い悪いではなく、根本的に別物であるということだ。本当に本当に自らが描いた1本の線を愛おしいと思ったことがあった。それは2度と描けない時と命の軌跡なのだ。

■日本画は岩絵の具を粉にして膠と水に溶かして作る。それを薄い色から望む色になるまで重ね塗る。最後の最後に輪郭を線で描く。色にも濃淡がある。これは日々繰り返して描くことで美しい線となる。書道にも似たタメとヌキ。力の入れ具合や遅速具合。呼吸が定まらないと望むとおりの線は描けない。緊張感と自在な弛緩。息を止めて自在に描く。私はペン画のマンガ描きでその感覚の一端を体感したと思う。
■描き慣れるには描き込む時間と量が必要だ。慣れてきてペンタッチやその人の絵柄が出てくる頃の1本1本の線の美しさは色っぽさすら感じる。描いている当人はその1本1本を意識して入るわけではないのだけれど、技芸であり職人であり芸術なのだと思わせる作家は少なくない。しかもマンガはそこに自らの哲学や理想を入れた話の語り手としての才覚すらも持ち合わせている。日本がクールな一端を担うわけだ。
2007.02.10 Saturday

 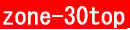 
|