#178 チッチー

■ものごころがついた時から、いつもそばには猫がいた。井の頭公園のそばで生活していた時も猫がいた。病気がちで、いつまでも大きくならない白黒のブチ猫。名前をチッチーといった。ある真冬の深夜、そのチッチーがアルミサッシの戸の透き間からひょろりと出ていき、車に撥ねられた。悲鳴を聞いて外に飛び出した私は、道の端にぼろぞうきんのような塊を発見した。一見しただけでもう助からないと分かった。
■しかしまだ絶命していないその猫を私は抱きかかえて部屋の中に運んだ。
だんだん硬くなっていく体をマッサージしながら、私は何が起こったのか実感が湧かずに、ただ静かに見つめていた。口や鼻から体液が止まらず流れ出している。その猫が力を振り絞って長い鳴き声をあげた。その冷たい空気を震わせる振動が最後の一声なのだと直感的に分かった。言葉にならない情動が私の身を包んだ。
■私はこの猫にできるだけの接し方をしていたので、ああすればよかったとか、こうしてやればよかったなどという悔いは何もなかった。ただ何か夢の中にいるような気がした。そのままその横で朝まで眠り、目が覚めてから死後硬直で突っ張った亡骸を、狭い庭に深い穴を掘って埋めた。その日から窓辺で音がすると、反射的にアルミサッシの戸を開けてあげる癖が残っている自分に、何度も何度も気がついた。
■1週間後、ようやく物音がしてもアルミサッシに手を掛けなくなった自分に気がついたその瞬間、胸のところにマヒしていた感情が堰を切ったように溢れ返り、涙がどっと込み上げてきた。その時初めてあの猫が本当に死んでしまったのだという事実を実感した。そしてあの最後の一声を自らの内側でこう理解した。「私の死を辛がったりしないで、これを反転して生きる力に変えて!もし思い出して悲しむのなら、忘れてしまって!」
■私はアルミサッシの戸を大きく開け放ち、その言葉の意味を噛み締めつつ何度も繰り返した。窓の外の植え込みの緑がゆるやかに風になびいていた。最後に抱き締めた時の感触が手のひらによみがえって来た。目に見えない純粋な感謝の塊が、私の中を抜けていった。冬の弱日がその手のひらに温かかった。
■私は今でもたまにその猫の事を思い出す。胸の痛みと共に思い出す。「私は約束した。思い出すたびに、悲しむのではなく、素直に一生懸命生きるのだと決意し直す事を。」ここにも反転の発想があると感じている。そして過去の思い出にこもるのではなく、あの猫を今でも愛しているがゆえに、この今から未来へ続く生き方のエネルギーとしようと繰り返し決心するのだ。
rewritten and replaced
2006.08.12
Saturday

 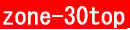 
|