#129 私を見守る「それ」は私自身

■魑魅魍魎、妖怪、天使、妖精、霊的存在、宇宙人、異次元人、未来人、エンティティ…。可知と不可知帯域のあわいに生ずる認識もしくは知覚される「何か」をおろそかにも誇張誇大化することもなく、できる限り真正に接しよう。こちらの生命振動がしかるべき方向から大きく外れていたりしなければ、その現象もしくは「何か」は決して邪魔をしたり害を与えたりするのではなく、力を貸してくれるはずだ。共にさらなる未来へとの約束。
■そしてその時その時の自分自身の状態と自分の総体の在りようについても気を配ろう。自らの想定やそれらと交わした約束を失念することなく生きよう。「これ」でも「あれ」でもない「それ」らはシンクロニシティとして演出してくれたり、思わぬ出来事としてその力や響きを意識と無意識のあわいで示してくれる。「これ」も「あれ」も「それ」も実はみな私の総体の一面だ。そして問うことは私の総体は「どれ」なのかということだ。
■まだ小学校に入る前の子供の頃、遠い未来の自分自身もしくはその反映を感じていた。「それ」は最初からそこにいてそれをそう解したのではなく自ら創出したのだった。考えて部屋の上方から自分を見守っている未来の自分がいるのであれば、自分は安心して生きていける。目に見えないのは未来のテクノロジーが優れているからであって、今の自分が劣っているわけではないと自己設定したために、「それ」はそこに立ち上がったのだ。
■見えないまま、そして他者と共有できぬものとしての「それ」は、自己設定したものだと知りつつも、感じようと思えば感じられた。感受性が強かった子供として1人夜道を歩く時でも、「それ」をそこに呼び出せば怖くはなかった。自分が創ったはずなのに、それはだんだん私と関係なくそこにいるように思えてきた。いろいろなことを教えてくれた。それは他ならぬ未来の自分自身だったと思い込んでいたからどちらでもよかったのだ。

■それを自分の力として他者を支配したり自信を増強したりするために使うより、むしろ自らの居住まいを正し自らを見守る温かく力強い存在として接するようになっていった。感謝と信頼の対象として扱え続けることができたのは、自分自身からの恩寵である。よくあるように、成長する過程でそれは段々立ち消えになっていったのではない。実は中学2年の頃、このままでは人生が面白来ないからとその存在を自ら忘れることにしたのだ。
■忘れようと決意して忘れることなどできるのだろうか。できる。それは忘れるのではなく、その存在を記憶しているとどうしても破れない限界を自ら破るために否定するのである。ただし感謝と共に。そしてここが少しコツがあるのだが、忘れるもしくは否定しさるとしても、それは必ず意識的に敢えてやったことなので、本当はそのもう1つ奥でそのこと自体をいつか必ず思い出すという設定を自らの意識深層にしていたということだ。
■そして思い出したのはずっと後の話となる。これを今はこのように客観的に描いてはいるがフィクションではない。しかしもう「それ」が本当にいたのかいなかったのか、自分が創ったのか創ったつもりになっていただけなのかは問題ではなくなっている。「それ」は今でも呼び出せるけれど、もはや私の本質的なところの形成には役立ったとしても、今は大好きな過去の遺物だ。たよることもないし、自分以外の何かと思うこともない。
■未来の私はまだ多分未だ捉えがたき総体として「そこ」にいるであろうし、過去の自分はこの今の私にすらも大切に思って欲しいのであろうし、否定せず他ならぬ自分自身としてこの上もなく慈しんでいる。他者と共有できないのは残念だが、他者のそのようなものを敬愛する余地は私の心にある。思い出す度美しく優しい世界にいて、それをあえて気づかぬまま喜怒哀楽を楽しんでいた私がいる。今ここにいる私はだれだろう。楽しんでいるか。いる。
2006.06.06.24
Saturday

 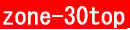 
|