#118 時超えて
ひとつとならん 加害心

■小学校に入る以前の子供の頃のある暑い夏、私は母の実家の新潟は柏崎というところの山中の田舎にいた。夏はセミが無数に鳴き交わしていた。蝉時雨などというものではない。蝉瀑布とでも言いたいほどだった。私は虫取りアミを抱えて近くのフルヤシキという半島のように平地から切り立ったままの小さな森に行った。この名前は昔は古い屋敷でもあったのだろうか。そこに従弟や弟と色々な物を持参して秘密基地を作ったりもした。
■アブラゼミは木の下から見上げると、鳴き止まぬまま木の幹を横ずりしてこちらの視角から逃れようとしていた。ニイニイゼミも体が小さい割りにかなりその声はうるさい。ツクツクボウシは羽が透けているので、鳴いている時に腹尻部を賢明に動かしているのがよく見える。たまにクマゼミがャワシャワと鳴いて周囲を圧倒する。夕刻にヒグラシが赤っぽい陽光を反射して哀調を伸ばしつつ鳴くようになると、秋遠からずと子供心に感じたものだ。
■そのフルヤシキでつかまえてきた数十匹のアブラゼミをみんな、縁側の簾の内側に掴ませらてみた。虫嫌いの人には不快な図であろう。横ずりしていって簾から飛び逃げていくセミもいた。私は突然その1匹に手を伸ばすと、その足をみな揉み千切ってから空に放り投げた。子供は残酷であるとよく言う。私はただ、足がなかったらセミは空中でホバリングしながら樹液を吸うことができるのか知りたかったのだ。思ったらもう動いていた。
■私はまだ他者の苦痛を知らなかった。他者他物への同情や共感の能力は、同じ年頃の子供より劣っていただろう。木の幹に止まろうとして、滑り落ちてはまた舞い上がるセミ。何度も何度もそれを繰り返すその姿を見て、私は初めて心の中に痛みを感じた。セミはやがて見えないところに飛び去った。庭先に残された私は、セミが何年も地中にいて地上に出てからはわずかしか生きられないということを思い出した。…少し悔いた。
■その夏はそれこそ無尽蔵に発生して、夏の日々を重くするほど鳴き交わすセミたち。そのうちのほんの1匹くらいなら別にいいだろうと思っていた。いやあまり深く考えてすらいなかった。それは今も間違いだと思っている。思い出すたびに胸の痛みは再現される。記憶というものが想起するたびに強化されるものだとすれば、私はこの痛みを頼りにして、小さな生命に対しての思いやりや慈しみを忘れないようにしようと自らに言い聞かせた。

■思い出せば自分はいつでも意識的にも無意識的にも限りなく他者他物に害を加えてきた。それはほかの何ものでも相殺できない私の心中の負の財産だ。1つ1つ、記憶の闇の中に沈めこむことなく想起し、そして負を反転させて未知の未来と現在に連結させるよう努めたい。登校途中の雨の中、擦り寄ってきた仔猫を水溜りに放り投げた自分。好きな女の子と入った喫茶店で話しかけてきてくれた小中学校時の友人をうるさく思って無視した自分。
■父に、母に、兄弟に、友人知人に、見知らぬ人たちに、自分はたくさんの酷いことをし続けてきた。しかし自らのうちに原罪や性悪説的なものを認めるつもりはない。それでも自覚できないエッジ、自分の意識辺境やその向こう側で多大な過去の遺産と遺物に影響を受けているのは間違いないのだから、その意識と無意識の混在した今、自分の生命ベクトルを良く見極め、全責任をとるつもりで時空を行こう。私と交差してくれた事実を輝かせるために。
■この話を読んでくれた他者が、その内容を不快がるとしたら、本当に申し訳ない。目的は不快な想いをさせることではなかったのだ。1つの反転の仕方、抜け方を自分自身のために記しておきたかったのだ。酷いことをしてしまった記憶の中の生命たち。もうとうにこの世にはなくなってしまった命たち。また今謝ったとしても、当人たちにはすでにさほど不快ではなくなっているか、最初から問題ですらなかったりもするだろう。
■しかし自分の中で未解決であれば、それは残る。この記憶を唾棄すべきものとか拭い去りたい汚点と判ずるのではなく、人間としての記憶の恩寵として扱い、そこから幾たびも幾たびも自らを自らの望む方向への純化の糧として巡らせ続けよう。その記憶が私の中で昇天する時まで。それは霊的存在と称する未統合の私や、統合から外された過去の私でもある魑魅魍魎たちとの約束でもある。「ごめんなさい。そしてありがとう。今はもう1つです。」
2006.06.13
Tuesday

 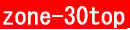 
|