#075 一二三四を
掌に載せ ひと飲みに

■「我思う、故に我あり」…そう、デカルトだ。5感で捉えたことはあてにならないが、自分の意識そのものは少なくとも自分自身に対して確実な存在であるという主張。しかしそれは自身に対してであって、他者には不確実なのだ。デカルトは窓の外を行く人たちは実は機械ではないかとも言っている。他人の自我の有無が判定できないということは、その実、自我の有無が判定できないからではないか?
■『荘子』斉物論第2にある有名な話。荘子は自分が蝶になった夢を見た。のびのびと楽しく飛び回り、自分が荘子であるということをすっかり忘れていた。ところが目を覚ますと自分は荘子である。はたして荘子が蝶になった夢を見たのか、それとも蝶が荘子になった夢を見ているのか?いわゆる「胡蝶の夢」だ。現実感があり矛盾がなければ、そこに住む人にはその世界が現実か虚構か区別がつかない。
■また『荘子』秋水編第17にはこんな話がある。荘氏と恵子が川遊びをしていた。(恵子とは高校の時に私が好きだった女の子の名前ではなく、ケイシと読む。立派な思想家だ。)荘子「魚が自由にのびのびと泳ぎ回っている。ああ、これこそ魚の楽しみだ。」恵子「君は魚ではない。何で魚の気持ちが分かるんだ?」荘子「そういう君は私ではない。どうして私に魚の気持ちが分からないといえるんだ?」
■私はこの荘子のなし崩し的に相殺させる切り返しが少し好きである。しかしこの返答は新しいフェイズを開く。つまり「分かる」と「分からない」から「分からないということが分からない」と「分かっているということが分からない」、さらに「分からないといことが分かる」と「分かっていることが分かる」の4値へ進みうるということだ。もちろんこれは「厳格な論理学的な話」ではなく「…話」の話だ。
■前提としている世界観や論理が間違っているか不完全であるという前提がないと、パラドクスとなる。「荘子が蝶になったのか、蝶が荘子になったのか」からその「どちらでもあり、かつどちらでもない」と「どちらでもない」が加わる4値論理へは、ほんの少しの跳躍だ。まあ「A」か「B」かに、「AかつB」と「どちらでもない」が加わるだけの話だ。ABには男女とか二元を入れればすぐ分かる。
■パラドクスや問いかけ自身に対して、その質や質問者そのものを問い直すのは、それがより真摯に返答するためのものであれば、問いかけそのものよりも論理階型が高い。ただの茶化しやなし崩し的リアクションと区別すること。いつまでも先哲の問いかけに掴まって最初のレベルでぐるぐる回るのはもういい。人の言うことを鵜呑みにするな。この私の言明すらも。このパラドクスを健やかに超えること。
2006.05.01
Monday

 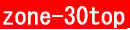 
|