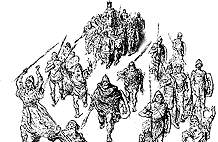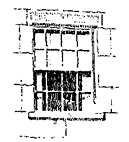水晶の国も雪が舞い始める季節になりました。お城には一人のお客がありました。東の国境を越えてやってきた若い詩人です。人生苦に満ちた顔ですが、時々優しそうに笑うその詩人を、ジュリアンとヴィオレッタはとても好きになりました。窓の外は銀色の雪が夢のように降っては積もっています。赤々と燃える暖炉のそばで、詩人は二人に東の国のことを語り始めました。
詩人は東の国のいろいろなものを見せては、それにまつわる話を語ります。ジュリアンとヴィオレッタは顔を紅潮させて聞き入るのでした。そのうちにヴィオレッタは、詩人の腰紐に縛ってある二個つづりの緋色のくるみに気づきました。ヴィオリッタがそれは何ですかと尋ねると、詩人は答えました。
「ああ、このくるみね。これは花の精がくれた火打石なんだ。暑い真夏にね、緋色の花がしおれて枯れかけいたんだ。その花があんまりきれいなんで、ぼくは山を三つ、野原を二つ越えて水を汲み、また戻ってその花にたっぷりかけてあげたのさ。するとどうだろう、真っ白い肌に紅炎色の長い髪をした花の精が現れて、綿のような笑みを浮べながらお礼を言うじゃないか。そうしていずれ役に立ちますよと言って、このくるみ石をくれたのさ。」
二人は顔を合わせて「ふうん」と感心しました。詩人もこの二人のあどけない美しさにしばしこの世の苦悩を忘れて、晴れ晴れと笑うのでした。