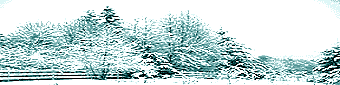![]()
![]()
![]() 真
白 い 部 屋 の 少 女
真
白 い 部 屋 の 少 女 ![]()
![]()
![]()
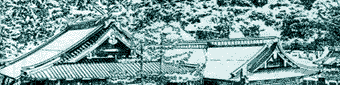
| 柳沢ちひろはその小学校の近所にある神社の娘だった。彼女は健太郎のクラスの子供達と一緒に、よくその広い境内で遊んでいた。みんなで遊ぶバレーボールで一番強烈なスパイクをするちひろが病弱な体質であるなどとは、誰一人知らなかった。それほどみんなの目にはちひろが快活に映っていたのだ。 石渡健太郎は二学期のクラス委員改選で、思いがけず副学級委員に選出された。元来反骨精神を肩にしょっている健太郎ではあるが、今回彼はその役職を甘んじて引き受けた。なぜなら学級委員の唐沢なぎさが飛び切りの美人だったからだ。彼は本意不本意織り交ぜてよく働いた。そんな彼を遊び仲間の男達は茶化し、半ば羨ましそうに嘲笑したが、健太郎は一向に気に懸けなかった。 さんなある日、柳沢ちひろが授業中に突然倒れて入院した。五年二組のクラス会は代表を見舞いに送ることに決め、そのクラス代表に正副学級委員を選定した。健太郎は美しく賢い唐沢なぎさと校外まで公的に行動できることを喜んだ。ちひろの症状なぞ露知らず、健太郎は浮かれながら病院の門を潜った。 ちひろのベッドは個室に据えられてあった。病室番号を頼りにそこに辿り付いた健太郎は、ちひろの病室のドアを開けて、なぎさとともにそこに足を踏み入れた。そこは白一色だった。壁の白。ベッドもシーツも白。窓の外にはご丁寧に雪まで舞っている。そして何よりも、セントラルヒーティングの半ば乾いて薬臭い空気の中で、その小さな病人の顔は蒼白だった。 その顔色に似合わずちひろは陽気に振る舞い、なぎさの横顔の方にばかり関心を払っていた健太郎は、千羽鶴を折ろうよと提案した学級委員の言に従い、不慣れな手つきで不細工な折鶴を作りつつ、三枚目の役を演じてその日を過ごした。 |
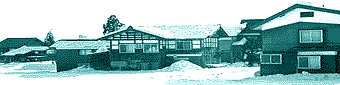
| ちひろの病気に対する関心もだんだん麻痺してきたある日、ちひろに心から同情していたクラス担任は、ちひろにみんなの寄せ書きを贈って元気付けようと教え子達に言った。五年二組の生徒達は彼女の発案に素直に従った。五年二組は5〜6人がひとつのグループになった班単位制をとっていた。その女担任が自腹を切って買って来た色紙を一枚ずつ与えられた各班は、それぞれの思いを一言ずつ添えて名前をしたためることになった。 健太郎の班は男三人女三人で構成されていて、彼自身はその班の班長も兼任していた。まず班長が色紙に筆を下ろし、それから班員のそれぞれが名を連ねることになっていたが、健太郎はいざペンを取る段になって、人並み月並みな言葉を書くのはつまらないと思い、深い考えもなくペンを走らせた。子供心に、何の罪の意識も感じないで書いた言葉はこうだった。 「早く死んでしまえ。」 学級委員の唐沢なぎさは、何も知らずに各班から書き上げられた色紙を集めて、担任の先生の机へと持っていった。クラス担任の先生は満足そうな面持ちで、それら一枚一枚を念入りに読んだ。健太郎たちは自分達の班の色紙を先生が読むのを待ち、にやにやしながら何かを期待した。 突然担任の先生の顔がさっと変わった。してやったりと喜ぶ暇もなく、先生は健太郎たちの班のところまでものすごい勢いで飛んできて、健太郎がその顔を覗き込むより早くその後頭部に手を宛がうや否や、思い切りその顔を机に打ちつけた。目から火が出た思いで赤くなった額と鼻の先に手を当てて痛がる健太郎の耳に、同じような音があと二つ飛び込んできた。何が何だか解らぬまま先生に向けた健太郎の大きな瞳に、担任の先生がその頬を涙でびしょびしょにしている顔が映った。 |

| 自分達の班の色紙がどうなったか健太郎は知らないし、知ろうとも思わなかった。冬も終わりに近づいたある日、健太郎はいつものように授業に聞き入っていた。ふいに誰かが教室のドアをノックする音がした。みんなが何かと思って見詰めると、入ってきたのは校長先生だった。ひきつった顔をして校長先生の話に頷く担任の先生を見て、クラス一同はぴんとある事実に気づいた。 やがてぎこちない足取りで教卓に辿り着き、ひじを机面に突き、両の震える手のひらを顔の前に組んで、担任の先生は喉から声を絞り出すような声で言った。 ほうけたように呆然とする健太郎の頭の中には、何ら納得のいく説明もないまま、それでも高鳴る胸を切り裂くように、それはリフレインした。 あの白い病室の中へと健太郎はどんどん沈み込んで行き、あたりはやがて真っ白になった。 19770328MON AM7:55 |