 #760
「もの」について考える(1) #760
「もの」について考える(1) 
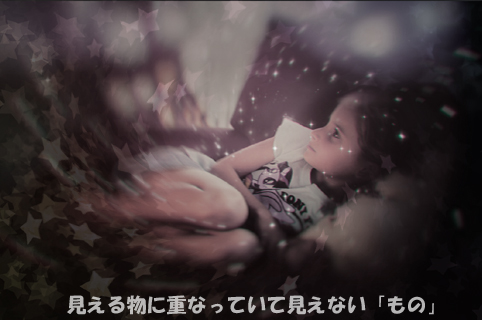
■1■歩きながらふと眼鏡を外してみた。それまで見えていた物たちの輪郭は多重にぼやけ、形の端から色が滲み出ている。距離感がおぼつかなくなる。それでも秋の日差しが肌に心地よいので、しばらくそのままゆっくり歩いてみる。ちなみに私の視力は0.01程らしいが、眼鏡を掛けるとまあ人並みに見える。
■2■人並みとは何だろう。現今の大多数の人たち程度にはということだろうか。アフリカの砂漠の民は視力が7.0あるとも言われ、また全く視覚的知覚が不可能な人もいる。過去の人たちはみな近視や弱視を知らなかったというわけでもない。大昔は眼鏡やコンタクトレンズのような視力矯正機器はなかった。
■3■現今の発想では視力2.0+の人は視力0.3の人より生活しやすかったと推測する。昔の人たちでも弱視の人はマイノリティだっただろう。だがその人たちは別の世界を見ていたかもしれない。全く物理的な光が見えない人は今でも別の世界に生きている。眼鏡を外せば今でも別の世界が見えるのではないか?
■4■「自己−他者」「自己−世界」に強力な意味を見出している欧米言語の中の自己他者問題では、「他者」や「物」と自己を明確に分別する。しかし私たちがほぼ無意識に使っている日本語には、物理的空間ではない「場所」や、物ではない「もの」等の言葉が、あられもなく存在し、そして機能している。
■5■「物悲しい」「物寂しい」(ものがなしい・ものさびしいと書いても同じ)と悲しい・寂しいは近似だろうか。前者の方がよりぼやっとして輪郭が定かでない。なんとなくという感じだ。これは比喩だが、眼鏡をしている時と外して世界を見た時の違いに似ている。「もの」のつく言葉は実に沢山ある。

■6■昔コンタクトレンズをしていた頃、意識的に片方だけ装着して生活してみたことがある。裸眼の左右で異なる感覚もしたが、そこまで厳密な実験をしたわけではないのでそこは捨ておくとして、数時間もしないうちにそれは馴染み慣れる。何かの拍子に片目が隠れた時に、片目裸眼なのだと改めて気付く。
■7■この実験をしていた頃は、社会生活で不自由な思いをした負け惜しみとはまた別の位相で、視力の弱い人は矯正可能なので、2つの世界の見え方を知っているが、目の良い人は1つの世界しか知らずにもったいないなと思った。知りたくて逆矯正の眼鏡を掛けると、すぐに気持ち悪くなってしまうだろう。
■8■日本語を用いる人は、「者」も「物」も「もの」もみな違うし、そしてまた同時にみな同じでもあることを、意識していなくても使いこなしている。「ものがたり」は何を語っているのか?主人公の主観世界か、第三者的な客観の事実か、語る者の史観や情感か?それらが非分離に語られているのである。
■9■日本の「侘び寂び」などと同様に語られる「もののあわれ」という言葉には、時代の変遷などもあって一言で定義できるものではないが、単なる主観や客観ではなく、語る者の内的心情とその照射だけに過ぎない世界の見え方ではなく、それらは元々分かちがたく一つであるところに用いられる物言いだ。
■10■「あなた」がいて「私」がいて、その間に世界があるというのも1つの世界観だが、「あなた」がいて「私」がいて、その双方を内包しつつ非分離な「場所」(世界)があるとした場合、私の「心」はどこにあるのだろう?私の外にある世界ではない、あなたと私も二而不二な場所にあるのではないか?
■11■場所に溢れ出て語る日本語には元来主語がない。述語的な物言いの中にものごとが語られ表出する。「もの」を物質世界の中の単なる物体として見るのではなく、見えている物や者を内包しつつ見えない「もの」として捉えようとすることで、奥行や幅や回転として表現されるものが掴めるかもしれない。
■12■ここで言わんとしていることは、目がよく見える方と見えない方のどちらが良いとか、日本語と欧米言語のどちらが良いという二択表現ではなく、双方を共に使う未知もあるということだ。2者を区別すると曖昧な部分が見える。そこを反転すれば2者を内包し、かつ超え行く方向性の存在の暗示である。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
■01■カルロス・カスタネダのドンファンシリーズの中で、夕やみ迫る黄昏の中で、カスタネダが得体の知れないカラスのような化け物だと思っていたものが、木に懸った黒い布切れだと分かってはしゃぐとき、呪術師ドンファンは「惜しかったな、もう少しのところでおまえは掴み損ねた」と言う場面がある。
■02■「幽霊の正体見たり枯尾花」は半面の真実を語りつつ、残る半面を断捨してまっている。正体の半分は恐れ怯えていた心が枯れ尾花を幽霊として見ていたことの自覚でもあろう。しかし物質主義を超えて、見えていたことは誤認や錯視ではなく、そのように見てた心の在りようにも半分の真実が存在する。
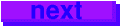  

|

