 #724
身体感覚が基底にある言葉 #724
身体感覚が基底にある言葉 
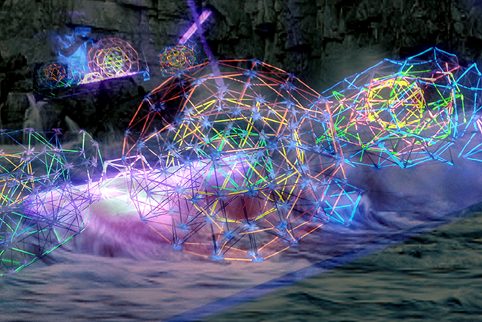
■1■既存ではない未知の概念には対応する言葉がない。そこでヌーソロジーは次々に新しい言葉を創出して、その概念をピン止めして前進し、また後からやって来る者のための里程標とする。詩人は既存の言葉に新しい意味を帯付して、それを未知の領域へ切り開いていく。しかしヌーソロジーでは混乱を招く。
■2■例えば「奥行き」と言う日本語に、既存の概念に上書きするように新しい概念を対応させる。言葉は意味と1対1対応ではないので、既存の概念と新しい概念が同じ言葉に同定されている。次元的に対立する言葉は「幅」だ。これが奥行きと対置されることによって、「幅」に否定的な語感が乗せられる。
■3■ヌーソロジー用語に日本語対応の日本語翻訳が必要となるわけだが、新しく創出もしくは想起された「語」と、既存の言葉に肩車させた新しい語義を併存させたままで、聞く者に提示するのは少し優しさに欠けている。確信犯的に突き進んでいるBOBはいいのだ。それを他者に伝えたい者の問題である。
■4■幼児たちは1歳半を過ぎると「なになに?」連呼の時代が始まる。見るもの聞くものがみな新鮮で、色々なものに眼差しを向け、手を伸ばして、飽くことなく「なに?」と問う。周りの大人は1つ1つその名を教える。ねこ。ちょうちょ。たまねぎ。おねえさん。存在の本質や意味ではなく名前を教える。
■5■幼児は名前を聞いて気が済むと、すぐに別のまだ未知なるものに興味を向ける。単なる音の並びではない肉声の響きに聞き耳を立てている。ものと言葉の重なった感触を、自らが様々なものに対して為した舐め回しや撫で回しの感触を元に、根源的類似をもって大脳皮質の連合野で統合しているのだろう。
■6■象徴や抽象概念に対する言葉は、目に見え手に触れることのできるものたちの名前とは少し勝手が異なるが、それでも腑に落ちる語感とどうしてもそぐわない語感とがある。幼児は自分に響かないものの名前を教えようとしてもなかなか興味を示さない。それを愚かだと思う大人は何かを忘れているのか。
■7■言葉が未発達だった黎明期には、感情や想いがそのまま「顔つき」となって語り掛けたことだろう。やがて咽頭腔・口腔・鼻腔から独自の響きに意味を持たせた言葉として語り掛けただろう。生物学的にエラに由来する鰓腸から声を出す。舌以外の顔面の表情筋もまた、全部鰓の筋肉由来の内臓系である。
■8■最も鋭い内臓感覚を持つ唇と舌で母親の乳首を吸った幼児は、生後6か月が過ぎて首が座ると、手当たり次第に周りのものを舐め回す。そして這い回りものを触りまくる。さらにはものたちを眼差しで舐め回す。これらの生体感触を基底にして、私たち1人1人は1つ1つの言葉を体得してきたのである。
■9■口下手を恥じる必要はない。心と身体感覚のない言葉を安易に吐くことを恥じ入るべきだ。思いと共に発声する時、内臓触角と共にその響きを聴きいる時、思考や論理や知性のその奥にある生命感覚を失念すまい。感受力を持ってBOBの言葉を聞いてみよう。それでも響かなければBOBの責任である。
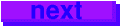  

|

