  (434)天体の運行に見る819日周期 (434)天体の運行に見る819日周期
次に天体に目を向けてみよう。土星の自転周期は地球の1日に対して0.444≒4/9である。これはどう言うことかというと、地球より自転のスピードが早い土星は地球が4回自転する間に9回自転するということだ。別の言い方をすれば、地球が1年に364回自転する間に土星は819回自転するということになる。すなわち364×9/4=819なのである。これはまた逆に見れば、地球の公転周期364日とマヤの819日周期暦との比率が4:9であるということでもある。
(1)地球の自転周期1:土星の自転周期0.444=4:9=364:819
(2)地球の公転周期365日:マヤの819日周期=4:9
また月の公転・自転周期は27.3日だが、819はこのちょうど30倍である(3)。マヤの神聖暦ツォルキンの260に、同じくマヤの天の神の数13を足した数である273は月の公転・自転周期27.3日のちょうど10倍である(4)。この1年364日に対してちょうど3/4である273の3倍が819なのである。そしてツォルキン260日の3倍は780日で、こちらは火星の会合周期となっているのだ。
(3)819=宇宙の背景輻射(2.73)X300
(4)819=月の公転・自転周期(27.3日)X30
(5)819=地球の1年の3/4(273日)X3
(6)火星会合周期(780日)=神聖暦ツォルキン(260日)X3
さらにこの819を円周率πで割ると260.6958…で、神聖暦ツォルキンの260に近似する(7)。この関係は地球の1年365日を円周率πで割ると116.183…で、水星の会合周期116日に極似することと相似形である(8)。なお819は1金星日の日にちでもある117の7倍である(9)。この117はまた、水星の会合周期116日に1を足した数でもある。さらに加えて言えばこの819日周期はその水星の自転周期58.5日のぴったり14倍になっている(10)。
(7)819=260Xπ
(8)365=116Xπ
(9)819=1金星日(117日)X7=水星会合周期{(116日)+1}X7
(10)819=水星の自転周期(58.5日)X14
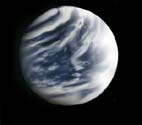 ここで金星との関係を見てみると、この819日と金星の会合周期584日の比率はほぼ5:7になっている(正確には585日、すなわち584+1日とちょうど5:7である)。この関係と全く同じなのが、地球の1年である364日とツォルキン260日との比率であり、これまたちょうど5:7になっている。ちなみに地球の1年である364日と金星の会合周期584日の比率は5:8である。さてでは先に神聖暦ツォルキン260日と農耕暦365日と金星暦(金星会合周期)584日の3組みの関係を見たように、ここではこのマヤの819日周期と地球の1年364日と金星公転周期225日との3組みの関係を見てみよう。この819日を地球の1年364日で割ると2.25で、ちょうど金星の自転周期225日の1/100となる。またこの819日を金星の自転周期225日で割ると3.64で、ちょうど地球の1年364日の1/100となる。別の表現をすれば、地球の1年364日と金星の自転周期225日の積は819日周期の100倍になっているということである。これらのことはそれぞれの比率が819:364=225:100=9:4になっていることからの当然の帰結である。しかしそもそもなぜそうなっているかということの「当然の帰結」は誰も説明できない。 ここで金星との関係を見てみると、この819日と金星の会合周期584日の比率はほぼ5:7になっている(正確には585日、すなわち584+1日とちょうど5:7である)。この関係と全く同じなのが、地球の1年である364日とツォルキン260日との比率であり、これまたちょうど5:7になっている。ちなみに地球の1年である364日と金星の会合周期584日の比率は5:8である。さてでは先に神聖暦ツォルキン260日と農耕暦365日と金星暦(金星会合周期)584日の3組みの関係を見たように、ここではこのマヤの819日周期と地球の1年364日と金星公転周期225日との3組みの関係を見てみよう。この819日を地球の1年364日で割ると2.25で、ちょうど金星の自転周期225日の1/100となる。またこの819日を金星の自転周期225日で割ると3.64で、ちょうど地球の1年364日の1/100となる。別の表現をすれば、地球の1年364日と金星の自転周期225日の積は819日周期の100倍になっているということである。これらのことはそれぞれの比率が819:364=225:100=9:4になっていることからの当然の帰結である。しかしそもそもなぜそうなっているかということの「当然の帰結」は誰も説明できない。
(11)金星会合周期(584日):マヤの特別周期(819日)=5:7
(12)神聖暦ツォルキン(260日):地球の1年(364日)=5:7
(13)地球の公転周期(364日):金星会合周期(584日)=5:8
(14)819÷364=2.25
(15)819÷225=3.64
(16)819:364=225:100
付け加えて言えば、この225:100は152:102でもあり、また9:4が32:22でもあることから、累乗関係の方向も内包している。例えば土星の体積は地球の体積を1とした場合その745倍なのだが、この数値は月の公転・自転周期27.3日の2乗745.29に極似しているが、このような方向における関係性を見る場合にも、累乗間の比率などの発想も不可欠となってくるだろう。なお水星の自転周期58.5日は、金星の会合周期584日と10進法的ホロンの関係にある。つまり金星が地球と1回会合する間に、水星は10回自転し、また5回地球と会合する。そしてその間に月は20回朔望するのである。これらのことなどからマヤ人があれほど熱心に金星を観測していた理由のほんの一端でも垣間見れれば良いのだが。
また819の10進法ホロン8190について言えば、まず13×14×15の3倍である。13×14×15は2730で月の公転・自転周期の100倍である(17)。また8190は2の13乗から2を引いた数である(18)。そしてまた8190は91の平方から91を引いた数、つまり91×90でもある(19)。そして91と90の平均90.5の2乗は8190.25となる(20)。
(17)8190=(13×14×15)×3
(18)8190=213−2
(19)8190=912−91=91×90
(20)8190=90.52−0.52
マヤ人がそのように用いていたかどうかは知らないが、819日周期暦は様々な惑星周期を約数として内包しているので、これをパラメーターとすれば相互間の数比関係をたやすく見て取れる。実際のマヤの重要な日付の間には、この819日周期の整数倍の関係が見られる。最初にも述べたように、この819日周期サイクルは地域が限定されていることやその例が少ないことなどからほとんど重要視されていないが、少なくとも「マヤの世界観における天の神の数<13>と、地下世界の神の数<9>と、地上の人間もしくは神の数<7>が出会う数、つまり13×9×7=819なのだ」という程度の説明しかできないまま放置しておく類のものではないだろう。今後の研究を待つ。なお参考までにこの819日暦と13の倍数で見た諸周期の一覧を表しておく。
| 819日 |
マヤ特別周期暦 |
819=13×9×7 |
13×63 |
| 780日 |
火星会合周期 |
780=13×6×10 |
13×60 |
| 687日 |
火星公転周期 |
- |
13×52.846 |
| 584日 |
金星会合周期 |
584=13×9×5 |
13×45 |
| 365日 |
地球公転周期 |
- |
- |
| 364日 |
地球公転周期 |
364=13×4×7 |
13×28 |
| 355日 |
月の13公転周期 |
- |
13×27.3 |
| 354日 |
月の12太陰周期 |
354=12×29.5 |
- |
| 346.6日 |
地球食年 |
- |
13×26.66 |
| 334日 |
金星火星会合周期 |
- |
13×25.69 |
| 260日 |
マヤ神聖暦 |
260=13×4×5 |
13×20 |
| 243日 |
金星自転周期 |
243=6×6×3 |
13×18.7 |
| 225日 |
金星公転周期 |
225=15×15 |
13×17.3 |
| 144.6日 |
水星金星会合周期 |
144.6=12×12+1 |
13×11+1 |
| 130日 |
神聖暦の半分 |
130=13×2×5 |
13×10 |
| 116日 |
水星会合周期 |
116=13×3×3−1 |
13×9−1 |
| 101日 |
水星火星会合周期 |
- |
13×7.77 |
| 88日 |
水星公転周期 |
- |
13×6.77 |
| 58.5日 |
水星自転周期 |
- |
13×4.5 |
| 29.5日 |
月の朔望周期 |
- |
13×2.27 |
| 27.3日 |
月の公転自転周期 |
3.9×7 |
13×2.1 |
| 23.4度 |
地球赤道傾斜角 |
3.9×6 |
13×1.8 |
| 19.5度 |
地球正4面体過角 |
3.9×5 |
13×1.5 |
| 13日 |
正数最小基本単位 |
- |
13×1 |
| 1.3 |
最小基本単位 |
- |
13×0.1 |

|