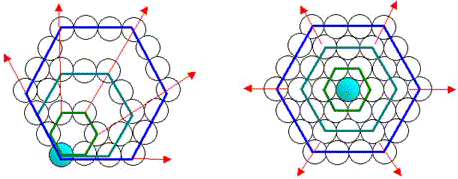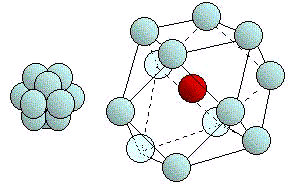「平面の充填」とは平面を任意の素材で隙間なく敷き詰めることであり、「空間の充填」とは同じく空間を任意の素材で隙間なく満たすことである。2次元を充填する素材を円とし、3次元を充填する素材を球体とする。スペースが残るがそもそも面積や体積を想定しない点の代用であったため、ここではそれについては言及しない。(こだわる人には最密パッキングの問題として考えていただこう。)さてここでまず2種類の6角数を考えてみよう。通常の6角数は6角形の一点から5方向に広がって行く。(上図左)そしてもう1つのそれは6角形の中心から水の波紋のように6方向に広がってていく。前者をただの「6角数」と呼び、後者を「波紋(状6角)数」と呼ぶことにし、ここでは後者を問題にする。この波紋状6角数が6方向、すなわち平面の全方向に広がって行き平面を満たしていく(もしくは塗りつぶしていく)のだが、その増加の仕方は次のようになっている。
次に空間充填のために、ベクトル平衡体の外殻数というものを考えてみよう。すでに何度か出てきているベクトル平衡体とは正6面体と正8面体の面点変換途中〔=中接球共有、すなわち線の中点共有)の平衡状態の形であり、正3角形と正4角形の平衡状態でもある。これは一意で3と4の平衡状態(3.65?)であり、また立体としては6と8の平衡である7と対応しているこの6と8の原子番号から炭素と酸素を想起させられ、また7からは呼吸に直接関係がないながらも大気中の大半を占めている窒素を連想する。さらに6+8=14から珪素をも思い出させられる。ベクトル平衡体がすっぽり収まる正6面体との体積比は5:6である。(5:6の比は太古のヤード83cmとメートル法の1m=100cmとの比率であり、5芒星と6芒星やバッキーボール〜サッカーボールの形をも連想させられる。)またベクトル平衡体の面14・点12・線24の総和は50であり、中心角は60度となっている。
|