#157 自らの生命をゆるやかに味わえば

■踏み出す足の一歩一歩、深く緩やかにする呼吸の一つ一つ、心臓の鼓動の一つ一つ、めぐらす思考の一つ一つが、本来あるべき私のありように比べると、まだまだ粗いと感じてしまった宵闇時。何者とも摩擦を生ぜず、何物とも相性が良く、自らの心すらも穏やかに静まりあって、ただこの次元の視座だけがある。あらゆる光を集めて、その美しい影にゆるやかにときめていてる命を自ら抱いて空気の中を進み行く。
■そんなに貪ることもなく、そんなに足早に急ぐこともなく、本当にゆっくりとこの世界を動き行くということ。私はそれほど高速で移動しなくても良いということを思い出した。本当に必要な時は何かが私を迅速に連れて行ってくれるはず。そんな風に考える人を、昔の私はおかしい人だと思っただろう。しかしその時の私もまた実はちょっとおかしかったということを、今の私は覚えているからどちらも愛しい。
■そんなふうに思い巡らせながら、いつもは立ち寄らぬ店に入って紫色した花束を買う。家に帰ったらあのガラスの花瓶に生けてみよう。お金と戦うわけでなく、お金から逃げるわけでもなく、ただ身の回りに流れるままにさせておこう。気が向けばちょっと押したり、引き寄せたりもできるのではあるけれど。流れをいじらず、流れに染まらず、ただその中で交わらず、摩擦も抵抗もないままに居るということ。
■緩やかに歩きながら考えることは足早に考えることよりも巡りが早い。繊細に動かしてみる体のあちこちを意識することは、あちこちの体の自然に動きたがっている感覚を少しずつ知ることができる。重力があればこそ、地上の生活は維持されている。重力は私たち人間の意識の総体であると友人は言った。重力の恩寵というフレーズを先達の詩人は教えてくれた。重力に沿って動かす体の心地よい回転感覚。

■呼吸は意識的にも無意識にでもできる界面行為だ。随意と不随意、機械と生命、条件反射と自由意志。その呼吸を用いて声を出し、意志を伝え合うという行為は本来、嘘や衒いや虚勢や自己憐憫のために用いるものではなかったのではないだろうか。あなたと私、ものと命、光と影、触れるものと触れられるものを繋ぐ神聖なものではなかっただろうか。呼吸を1つする度に生命は死へと向かう。愛しからずや。
■ゆっくり踏み出す足先を見詰めてみた。足先を気にすることは長いことなかった。十代の終わり頃に畳の上に横たわり、首をもたげて足先を眺めてみた。その足の指たちは遥か遠くにある感覚がしたことを思い出す。あの不思議な感覚。自らの体なのに、手を伸ばしてもいつまでも届かないつま先との距離感。苦節を耐えてきた足先に感謝の念が滲み出て行き渡る。同様に体の各所に対しても有難さが湧き上がる。
■ゆっくりと自らの両の手のひらを眺め見る。右手が愛おしくて左手で撫でてみた。その左手が健気に思えて右手でさすってみる。どちらも私の体なのだけれど、どちらも触れることができ、触れられることもできる素晴らしさ。共に1つに合わさって合掌することもできるけれど、それぞれがばらばらに体のあちこちを撫でさすり、癒し、元気付けることすらもできるという素晴らしさ。
■私は私を抱きしめることで、私は私に抱きしめられる。呪うことすらもできるけれど、私は祝い寿ぐ方を選択する。これは好みの問題かもしれないけれど、自らの好みすらも好ましい。本当にゆるやかな流れの中で、私は自らを予祝し、恩寵に満たされるであろうことを確約する。その思いで取って返して世界を寿ぎ、寿ぐことのできるこの身体があるという喜びに身を震わす。夜が降り、闇は満ち、時は巡る。
2006.07.22
Saturday

 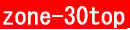 
|