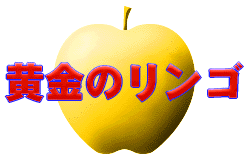
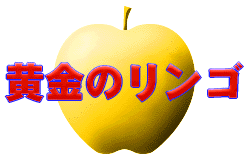
| 熱心な仏教者たち。彼女達のうちの幾人かは、もしモロッコに生まれたらマホメット教徒に、ロンドンに生まれたらキリスト教徒になっていただろう。しかし彼女らこそが、綿々と生を紡ぐのだ。 |
![]()
| 青春は人生の恥部だって?毛虫だって?毛虫の時代を経なければ蝶にはなれないだって?どこのくされ年寄りが言ったんだ?そいつは自分が蝶のつもりでいるのか?感性が鈍磨した老醜を憎悪するぜ。 |
![]()
| 苦痛は善か?苦痛が人の性格を強くするとの賛美は、裏を返せば苦しむ者は復讐を欲するということになり、自分が耐えている苦悶をあえて他人にも付与するための手前味噌ではあるまいか。大風呂敷に直に包めば臭いだけだ。 |
![]()
| 労働は神聖なり?無能なものは働いていないと退屈するからね。でも怠けているためには、多くの才能や教養、そして特殊な精神形態が必要だということも知るべきだ。そういう者は怠惰こそが神聖なりと、物憂げに言うだろう。実際、怠惰も労働の一つなのだから。 |
![]()
| こと女に関しては、浅い水溜りには目もくれず、深い淵の中へこれきりと身を躍らせ、かねてからの喉の渇きを満たそうとして、甘い蜜に喉を詰まられてしまい、死の手前まで行ってしまうような、そんな輩たち。しかし彼らこそが、連綿と生を伝えるのだ。 |
![]()
| 恋心ってやつは叱ったところでどうにもならない代物だから、恋に取り付かれちまった若者には、早いが珍重、やけどの薬。 |
![]()
| 「あれはこれに、それはあれに、これはそれにうまいこと取り替えるんだ。いいな、これが四元数ってやつだ。おい、わかったか。」 「へえ、ちっともわかりません。」 |
![]()
| 古代ギリシアの女預言者シビルに、アポロは彼女の手に握れる砂の粒だけの寿命を与えた。しかし年とともに褪せる色香を止める術は与えなかった。秋口の雷に呼応して猛り狂うアドリア海の大波を見詰めながら、シビルは自分のかくれもなき老醜をかんがみた。 |
![]()
| 年中めまいを感じている者には、世の中の方が回って見える。 |
![]()
| 19歳の頃、大きなファミリーレストランでアルバイトをしていた。ある日、コックとウェイター主任がまかないの食事を取りながら話をしているのが耳に入ってきた。なんでも知人の娘が交通事故で即死したらしい。その娘はうら若き17歳で、色白で美しく、末頼もしいと親も思っていたことや、小さな頃の思い出話をいくつもしていた。 妙に感動してしまい、泣きそうになって顔をしかめた。可笑しなことだった。知りもしない娘のために。何にそんなに打たれたのだろう。残された親達の嘆きを思ってだろうか。娘が大層な美人だったから惜しいと感じたのだろうか。それとも二人の会話の底に流れる、裏心のない同情心に共鳴だろうか。 その日は仕事を終えると早々に帰宅した。その夜、夢に出てきた、見たこともないその娘は大層美しかった。 |
![]()
| 部屋の中には暖炉が燃えていた。しかし窓の外は嵐の坩堝だった。気の触れた風が吹き荒れて、上空では八つ裂きにされた雲が苦悶するように身を捩り、紺と灰白にまだらな空を無言で押し流されていた。 次の日の朝、雨上がりの森を歩いてみた。水の流れた溝跡が柔土のあちらこちらにあり、湿った枯葉のあたりから、母なる大地の官能的な匂いが立ち昇っていた。 森の中は昨夜の嵐を忘れた、緑の錯綜だった。雨しずくの残った若葉は繊細な透かし細工で、淡緑の光が斜めに射す一面は茫漠とした別世界だった。神々しい静寂は心を洗い流し、命がそこでは純粋に燃える想いだった。 時として耳を快く驚かすものは、ブナの梢高く鳴く小鳥と、飛び回る栗鼠だけだった。さらに耳を澄まし心を澄ますと、牧場のはるかむこうでカッコウがこだまのように鳴いていた。谷の底にはまだ、すみれ色をした霧が消えやらずに佇んでいた。 |
![]()
| 今さら言うほどのことではないけれど、男らしさと女らしさの両突端は意識の外にあるので、純粋にして愚朴なものだろう。意識の強烈なる集中度に従って、性の中立へ限りなく接近する。ある者は性を超越しようとして倒錯者になる。またある者は脱落して精神的不能者になる。 無意識の中にこそ、完全なる美は存在する。代償として、無意識なる者は同等の醜悪をも提示する。白痴美は保護者を必要とする。意識過剰な者の創ろうとする美は、意識ゆえに完全ではない。限りなく完全に近づこうとする錬金術師は、しかしその生き様が美しい。生き様まで演出しようとする者はえせ者だ。自意識過剰の悪臭には、唾棄しても罪にはなるまい。 えてして男らしい男、女らしい女は、自分ではそれを正当に認識していないものだ。幸せな者に幸せという単語が必要ないように、美しい者におまえは美しいと告げる必要はない。その行為は美の破壊である。 |
![]()
| 風に揺れるきんぽうげの花は、緑の原に敷かれた黄金の絨毯だった。 |
![]()
| 立ち枯れの林の上を、喪服の切れ端のような大烏が、裸の枝々にからまりながら飛び交いながら、しわがれ声を黒雲に響かせて凄味をきかせている。 |
![]()
| 清く美しく死にゆくということは、後に残された者への愛ではなかろうか。僻見に寄れば無意味にも思えることだが、死後の自分には何の利点もないことだから。 |
![]()
| 高い樅の一群を、銀色の霧が舐めずりながら、傾斜した丘を這い上がっていく。その霧の境目を、黒いマントを羽織った気の違った若い詩人がさまよい歩いている。己れの歳を伸ばしすぎたと悲嘆にくれて、その死すべき柔床を探し求めて…。 |
![]()
| ダンデライオン。綿毛がそよ風に乗って漂っていく。時に身を委ねて無目的に、ただ肥沃な大地に種子を撒き散らし、また芽吹き、花咲き、実り、誰にも顧みられずに死んでいくために。 |
![]()
| 暮れかかる夕陽を追うように、谷から湧き上がる霧。その一粒一粒が夕陽に煌めき、黄金の塵がゆっくりと流れる。太陽は断末魔のおぼろな光を放ち、山の端に隠れる。待ち受けていたように大気はどんどん冷えていき、霧はその乳色のかいなの中へ地上の全てを抱え込む。その上を夜の闇帳が降る。静寂なる聖夜。 |
![]()
| 愛と美こそが、ノアが箱舟で船出するずっと前からの陪審員だったのだ。19の時の皆既日食に恐れをなしてから、臆病風に縛られて、その金と銀の色つやをむざむざと時にさらして、褪せ果てさせてしまったのだ。4年という星霜…。 |
![]()
| 「君の長く変わらぬ好意と誠実と友情が、今心の中で刈り入れ時を迎えているのに、君に何もしてあげられぬとは。感謝の気持ちほどにこの財布が重かったなら、充分なお礼も意のままなのに、本当にありがとうというただの言葉でしかすまされないとは、何という不幸だろう。」 「いいえ、その一言だけでもう、充分すぎるほど満足です。いつ死んでも悔いることすらありますまい。」 |
![]()
| へへん、いい気になるなよ。小夜鳥だって時には鴉に答えて鳴くものさ。 |
![]()
| 亡霊のような風が、透明の怪物のように落ち葉を掻き分けて、閑散とした林を抜けていく。明け方の空には移ろいやすいバラ色の茜雲がくっきりと層をなしている。時を告げる鐘の音が冷たい空気の中で、飛び回るハゲタカのようにこだましあう。 |
![]()
| 柔らかにして穏やかな色合いの、つつましい紫水晶を思わせるヒース。 |
![]()
| 雨上がりの澄んだ光の中で、萌え葉の水滴が碧玉の七色を放つ。自然の精緻を極めた豊かな色合いは、自己愛に夢中な者どもを飾る、あのけばけばしいにせ宝石の輝きとは較べものにならない深みを持っている。それはるり色を限りなく薄めたように半透明な木立ちと相まって、一つの完全なる幻想空間を創りだしていた。そこへ踏み込んだものを無言の陶酔に誘いこまずにはおかぬような空間を。 |
| 散文試詩集 「金色のりんご」1977,2,25完成 一人称を排除する試みと共に。 |